|
<北京は荒野?>
景山の高見から眺望する北京は、あくまで、整然としたたたずまいを誇り、王城の香気を放つ。前章はその魅力について言及した。しかし、この街の本当の魅力は、実のところ、「整然さ」だけにあるのではない。むしろ、そうではないことが、北京の魅力なのだ。
高見から地上に降り立ち、中軸線を一歩はずれる。すると、どうだ。そこには胡同が拡がっている。荒野のように。ひとつの胡同を進むと、いつか、別の胡同に繋がり、その先には、また、別の胡同が待っている。古来言う。「名の有る胡同で三百六十、名のない胡同は牛毛の如し」、と。しかし、実際はそんなものではない。三千ともいう。六千ともいう。それが、迷路のように繋がり合う。寛い胡同。狭い胡同。長い胡同。短い胡同。麻糸の乱れのように混沌としている。
 中軸線の整然と、胡同の混沌。
中軸線の整然と、胡同の混沌。
どちらに、より重きを置いてこの街は見られるべきなのだろうか。私には分からない。ただ分かっているのは、この整然も混沌も、ともに、北京であるということである。整然と混沌との渾然。総じていえば、この渾然こそが、北京という街なのではないか思う。
これは、都市設計者の意図したところだろうか。彼は、「整然」を目指し、結果として、「渾然」になったのだろうか? それとも、「渾然」こそが、設計の意図であったのだろうか?
姿形だけではない。そこにほどこされた色彩にしてもしかり。瑠璃の甍は黄金色に輝き、王城の香気を薫らせる。一方、その故宮を取り囲む胡同は、壁も屋根の瓦も灰色の煉瓦造り。灰色一色のなかに深く深く沈んでいる。
王城の輝きと市井の沈倫。
胡同を、何時間か、あてもなくふらつき廻ると分かる。灰色は、白よりも黒よりも色がない。無機そのものだ、と。
「よりによって、どうして街中をこんな色に塗りつぶしたんだ」
こんな疑問が、自ずと、湧いてくる。
「黄は皇帝の象徴。黄色を用いることができたのは皇帝だけ。同様に緑色の瑠璃瓦を葺くことは、皇族や親王だけに許されていた。庶民に許されたのは、灰色だけだった。だからだ」
いやいや、そんなことは私だって知っている。それでも、胡同を歩いていると、やはり同じ問いが頭をもたげてくる。街という街をこんな色にようとしたのは何故なのだ、と。
「王府井大街」から「北池子大街」あたりのくすんだ胡同を抜け、「東華門」に出ると、一瞬、驚きに捉えられる。聳え立つ高殿。黄の瓦、青と緑に飾られた梁、紅の壁。眼がビックリする。世界が、モノクロから、急に、総天然色に変わったみたいに。
「黄色と灰色を対比させ、皇帝の権威を示そうとした。だからだ」
いやいや、それも分かる。それでも、胡同を歩いていると、やはり同じ問いが頭をもたげてくる。街という街をこんな色にようとしたのは何故なのだ、と。
実のところ、私の言いたいことはこうだ。
北京人は、灰色を愛した。灰色一色の街に住みたいと願った。だから、胡同は、屋根も壁の灰色なのだ、と。
冬。胡同を歩いてみたらいい。空気はカラカラに乾燥している。木枯らしが吹き荒ぶ。木は葉を落とし尽くし、裸の枝が不機嫌気に揺れている。胡同のような狭い道に植えられているのは、必ずといってよいほど、落葉樹。それも、柳か槐(えんじゅ)。幹も枝も黒々としている。寒風に震えながら思うともなく思う。落葉樹であることも、色が黒いことも偶然ではないのだ、と。意識的に選んだんだ、と。木枯らしが吹き荒び、屋根も壁も灰色で、木々が黒々と蕭然とした姿で立っている。
 何という美しさ!
何という美しさ!
屋根の瓦も、壁の煉瓦も灰色でなければならない。木々の幹も枝も黒くなければならない。それが、彼らの美意識の表現でなくてなんだというのだ。
春先になる。強い西北の風が吹く。その風が黄砂を運んでくる。最近はそうでもないが、つい二、三十年前まで黄砂はたびたび北京の空を覆い尽くしたという。家にいると、昼間でも灯りをつけなければ本が読めなかったという。街にいると、十メートル先の人の顔の見分けが付かなかったという。黄色い風が吹き荒ぶ街。その時、壁の煉瓦は何色が似合うだろう。少なくとも、青や緑ではないだろう。
 そう、屋根の瓦も、壁の煉瓦も灰色でなければならない。木々の幹も枝も黒くなければならない。
そう、屋根の瓦も、壁の煉瓦も灰色でなければならない。木々の幹も枝も黒くなければならない。
街は、冬の木枯らしや春先の黄砂の荒らしに似合うように造られた。胡同を歩き回るうちに、だんだん、そう思えてくる。
皇帝が色を禁じたから、胡同は灰色になったという。そうだろうか? 私は、灰色の街が彼らの美意識だと思う。赤でも青でも好きな色を使ってよいと言われても、街は灰色になっていたと思う。
皇城の黄や赤を目立たせるために、街を灰色にしたという。そうだろうか? 逆の可能性はないだろうか。胡同の灰色を目立たせるために、皇城を黄や赤にした、と。
灰色の煉瓦に宿っているのは、おそらく、北方民族の血なのだ。先祖代々西北の砂漠に暮らしてきた人々の、故郷である荒野に対する思慕の念なのだ。彼らは、きっと、北京という大都会にあっても、砂漠の荒野を忘れまいとした。荒野を再現しようといした。砂漠に生まれ育った暗い眼が、灰色の街を造った。
北京に大規模な帝都を最初に造ったのは元王朝であった。彼らモンゴル人は、都市の大枠は中国人の発想をもって決めた。シーメトリーという整然だ。それが、鼓楼から永定門への中軸線であり、紫禁城である。同時に、その整然を、故郷の砂漠の荒野のイメージで取り囲み尽くしてみせた。胡同の果てしない灰色である。
私は、胡同を歩きながら、こんなことを夢想する。
ともかくも、シーメトリがと描きだす整然と、底のない混沌が、渾然と溶け合っている。それが、北京という城市である。黄金に輝く瑠璃の瓦が王城の気を薫らせ、その周りには、ビッシリと、荒野の無機が埋め尽くしている。それが、北京という城市である。
そんな街を語ってみたい。それが、私の『北京胡同物語』だ。
 北京という城市……そう、前にもこの城市という言葉を使った、こういう日本語はないのだろうか。中国語で「街」を「城」と言う。「国破れて山河あり 城春にして草木深し」、と。中国では、古来、都市は城壁で囲まれていた。どの都市もである。無論、外的から身を守るためである。北京も例外ではない。しかも帝都であったがために、幾重にも城壁が巡らされていた。皇帝の居城は紫禁城。先ず、この周りに高くて厚い壁がある。この紫禁城を包み込むのは皇城。ここには、皇帝が五穀豊穣を祈る場である社禝壇や皇帝の先祖を祀った太廟、御苑である北海、中南海が同時に包み込まれている。そして、その外にあるのが内城。役所があり、人々が居住する所謂街である。更に街を拡張するために内城の南に隣接して建設したのが外城。このように、北京という街は、幾重もの入れ子の構造で出来ている。しかも、そのすべてが、高く厚い城壁で囲まれていた。南から皇帝の居城に至ろうとすると……。先ず、外城に永定門から入る。次に、内城の門である正陽門をくぐり、皇城の門である天安門を通り、更に、紫禁城の入口である午門をくぐる。紫禁城を皇城が包み、皇城を内城が包み、内城を外城が包む。つまり、北京という街はは幾重もの城であった。今は、内城の城壁も、外城の城壁もないのだが……。 北京という城市……そう、前にもこの城市という言葉を使った、こういう日本語はないのだろうか。中国語で「街」を「城」と言う。「国破れて山河あり 城春にして草木深し」、と。中国では、古来、都市は城壁で囲まれていた。どの都市もである。無論、外的から身を守るためである。北京も例外ではない。しかも帝都であったがために、幾重にも城壁が巡らされていた。皇帝の居城は紫禁城。先ず、この周りに高くて厚い壁がある。この紫禁城を包み込むのは皇城。ここには、皇帝が五穀豊穣を祈る場である社禝壇や皇帝の先祖を祀った太廟、御苑である北海、中南海が同時に包み込まれている。そして、その外にあるのが内城。役所があり、人々が居住する所謂街である。更に街を拡張するために内城の南に隣接して建設したのが外城。このように、北京という街は、幾重もの入れ子の構造で出来ている。しかも、そのすべてが、高く厚い城壁で囲まれていた。南から皇帝の居城に至ろうとすると……。先ず、外城に永定門から入る。次に、内城の門である正陽門をくぐり、皇城の門である天安門を通り、更に、紫禁城の入口である午門をくぐる。紫禁城を皇城が包み、皇城を内城が包み、内城を外城が包む。つまり、北京という街はは幾重もの城であった。今は、内城の城壁も、外城の城壁もないのだが……。
 ……北京という城市の壮麗は、景山からの眺望に尽きる。
……北京という城市の壮麗は、景山からの眺望に尽きる。
景山。決して高い「山」ではない。人口の丘に過ぎない。しかし、ピタリっと、中軸線の線上に置かれている。しかも、中軸線上では、最も高い視点をもつ。頂に立ち、北を見やれば、寿皇殿の黄色い瑠璃瓦の屋根越しに真っ直ぐ北に伸びる鼓楼大街が、その余りの真っ直ぐさ故に眼に飛び込んでくるのである。そして、その先には鼓楼の緑の屋根と赤い柱が、その真っ直ぐな道を、真っ正面からピタリと遮っているのである。鼓楼大街を軸に、鼓楼に至るまでの建物は、すべて、これまたピタリと左右対称に出来上がっているのである。天気が良ければ、その遙か彼方には、燕山山脈が青く青く横たわっているのである。
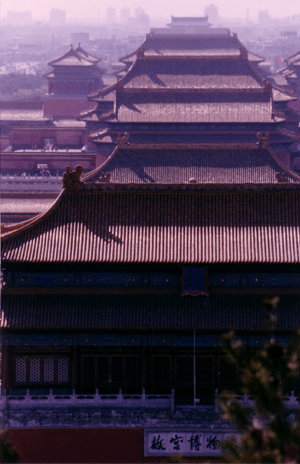 南を見やれば、故宮の黄色い瑠璃瓦の甍が眼下に広がっている。思わず息を呑む迫力だ。故宮の面積は七十二万平方メートルという。広いなんてもんじゃない。その敷地すべてが楼閣で埋め尽くされている。高いもの、低いもの。部屋の総数は九千という。多いなんてもんじゃない。その楼閣のすべてが黄色い瑠璃瓦で被われている。甍が大きな波を打ち、大きな波のなかに小さな漣がたち、一枚一枚の瓦のすべてが太陽の光のなかで輝いている。それを、取り囲む壁は鈍い赤……。そこに、一本の線が見える。故宮の北端の門である神武門から保和殿から太和殿、故宮の南端の門・午門を越え、更に遠くに霞むのは、内城と外城の境、正陽門。その線を軸に、左右は、ピタリと対称形をなしている。 南を見やれば、故宮の黄色い瑠璃瓦の甍が眼下に広がっている。思わず息を呑む迫力だ。故宮の面積は七十二万平方メートルという。広いなんてもんじゃない。その敷地すべてが楼閣で埋め尽くされている。高いもの、低いもの。部屋の総数は九千という。多いなんてもんじゃない。その楼閣のすべてが黄色い瑠璃瓦で被われている。甍が大きな波を打ち、大きな波のなかに小さな漣がたち、一枚一枚の瓦のすべてが太陽の光のなかで輝いている。それを、取り囲む壁は鈍い赤……。そこに、一本の線が見える。故宮の北端の門である神武門から保和殿から太和殿、故宮の南端の門・午門を越え、更に遠くに霞むのは、内城と外城の境、正陽門。その線を軸に、左右は、ピタリと対称形をなしている。
 よくぞ、ここまで……。
よくぞ、ここまで……。
自然の一部の如くに途方もなく広く拡がり、しかも整然と左右対称に配置されている。何と言えばいいのだろう。その黄金色に光り輝く瑠璃の瓦から、王城の気が立ちのぼっているを感じないわけに行かない。剛毅に気高く堂々と。景山の頂に立つとき、私たちは、そのことに驚かされるのだ。世の中にこんなものがあったのだ、と。
そう。シーメトリーは、中国人の世界観における、ひとつの夢の形なのだろうか?
|
 中軸線の整然と、胡同の混沌。
中軸線の整然と、胡同の混沌。 何という美しさ!
何という美しさ! そう、屋根の瓦も、壁の煉瓦も灰色でなければならない。木々の幹も枝も黒くなければならない。
そう、屋根の瓦も、壁の煉瓦も灰色でなければならない。木々の幹も枝も黒くなければならない。 北京という城市……そう、前にもこの城市という言葉を使った、こういう日本語はないのだろうか。中国語で「街」を「城」と言う。「国破れて山河あり 城春にして草木深し」、と。中国では、古来、都市は城壁で囲まれていた。どの都市もである。無論、外的から身を守るためである。北京も例外ではない。しかも帝都であったがために、幾重にも城壁が巡らされていた。皇帝の居城は紫禁城。先ず、この周りに高くて厚い壁がある。この紫禁城を包み込むのは皇城。ここには、皇帝が五穀豊穣を祈る場である社禝壇や皇帝の先祖を祀った太廟、御苑である北海、中南海が同時に包み込まれている。そして、その外にあるのが内城。役所があり、人々が居住する所謂街である。更に街を拡張するために内城の南に隣接して建設したのが外城。このように、北京という街は、幾重もの入れ子の構造で出来ている。しかも、そのすべてが、高く厚い城壁で囲まれていた。南から皇帝の居城に至ろうとすると……。先ず、外城に永定門から入る。次に、内城の門である正陽門をくぐり、皇城の門である天安門を通り、更に、紫禁城の入口である午門をくぐる。紫禁城を皇城が包み、皇城を内城が包み、内城を外城が包む。つまり、北京という街はは幾重もの城であった。今は、内城の城壁も、外城の城壁もないのだが……。
北京という城市……そう、前にもこの城市という言葉を使った、こういう日本語はないのだろうか。中国語で「街」を「城」と言う。「国破れて山河あり 城春にして草木深し」、と。中国では、古来、都市は城壁で囲まれていた。どの都市もである。無論、外的から身を守るためである。北京も例外ではない。しかも帝都であったがために、幾重にも城壁が巡らされていた。皇帝の居城は紫禁城。先ず、この周りに高くて厚い壁がある。この紫禁城を包み込むのは皇城。ここには、皇帝が五穀豊穣を祈る場である社禝壇や皇帝の先祖を祀った太廟、御苑である北海、中南海が同時に包み込まれている。そして、その外にあるのが内城。役所があり、人々が居住する所謂街である。更に街を拡張するために内城の南に隣接して建設したのが外城。このように、北京という街は、幾重もの入れ子の構造で出来ている。しかも、そのすべてが、高く厚い城壁で囲まれていた。南から皇帝の居城に至ろうとすると……。先ず、外城に永定門から入る。次に、内城の門である正陽門をくぐり、皇城の門である天安門を通り、更に、紫禁城の入口である午門をくぐる。紫禁城を皇城が包み、皇城を内城が包み、内城を外城が包む。つまり、北京という街はは幾重もの城であった。今は、内城の城壁も、外城の城壁もないのだが……。 ……北京という城市の壮麗は、景山からの眺望に尽きる。
……北京という城市の壮麗は、景山からの眺望に尽きる。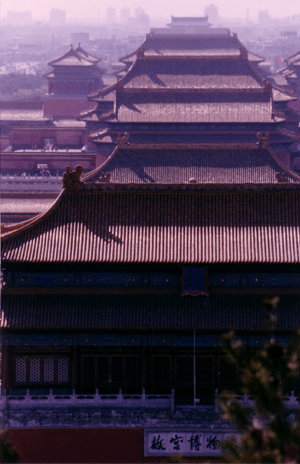 南を見やれば、故宮の黄色い瑠璃瓦の甍が眼下に広がっている。思わず息を呑む迫力だ。故宮の面積は七十二万平方メートルという。広いなんてもんじゃない。その敷地すべてが楼閣で埋め尽くされている。高いもの、低いもの。部屋の総数は九千という。多いなんてもんじゃない。その楼閣のすべてが黄色い瑠璃瓦で被われている。甍が大きな波を打ち、大きな波のなかに小さな漣がたち、一枚一枚の瓦のすべてが太陽の光のなかで輝いている。それを、取り囲む壁は鈍い赤……。そこに、一本の線が見える。故宮の北端の門である神武門から保和殿から太和殿、故宮の南端の門・午門を越え、更に遠くに霞むのは、内城と外城の境、正陽門。その線を軸に、左右は、ピタリと対称形をなしている。
南を見やれば、故宮の黄色い瑠璃瓦の甍が眼下に広がっている。思わず息を呑む迫力だ。故宮の面積は七十二万平方メートルという。広いなんてもんじゃない。その敷地すべてが楼閣で埋め尽くされている。高いもの、低いもの。部屋の総数は九千という。多いなんてもんじゃない。その楼閣のすべてが黄色い瑠璃瓦で被われている。甍が大きな波を打ち、大きな波のなかに小さな漣がたち、一枚一枚の瓦のすべてが太陽の光のなかで輝いている。それを、取り囲む壁は鈍い赤……。そこに、一本の線が見える。故宮の北端の門である神武門から保和殿から太和殿、故宮の南端の門・午門を越え、更に遠くに霞むのは、内城と外城の境、正陽門。その線を軸に、左右は、ピタリと対称形をなしている。 よくぞ、ここまで……。
よくぞ、ここまで……。