
|
|
===浙江省===
|
|
《杭州》(こうしゅう)
 杭州は浙江省の省都。杭州湾の最も奥まったところ、銭塘江の左岸に開けた町である。
杭州は浙江省の省都。杭州湾の最も奥まったところ、銭塘江の左岸に開けた町である。
秦の時代、始皇帝が銭塘県を設置したのが史書にこの地が登場する始まりだという。隋には北京から黄河、長江を越え杭州に至る京杭大運河が開削されてからは、江南の重要な拠点となりる。
江南の憶ひ
最も憶ふは 是れ 杭州
山寺の 月中に 桂子を尋ね
郡亭の 枕上に 潮頭を看る
何れの日か 更に 重ねて游ばん
唐の詩人・白居易の詩である。白居易は左遷され杭州で刺史を務めていたことがあった。後日その日々を振り返り感慨を述べたものである。「最も想うのは杭州である」、と。
「山寺」は杭州の霊隠寺または天竺寺を指し、「桂子を尋ね」とは、月に生えるという桂の実をさがすことを言う。「群亭」とは役所にある亭であり、寝ながらに銭塘江の逆流を見ることを言う。
時代が下り、南宋(1127~1280年)の時代には、都が杭州に置かれる。十三世紀マルコポーロが訪れ、その繁栄ぶりを「まちがいもなく世界第一の豪華・富裕な都市」(平凡社・『東方見聞録』、愛宕松男訳)と記す。
町は西湖を抱くように広がるが、西湖の名の由来は西施にあるという。春秋時代、越王・勾践が、宿敵呉の夫差を滅ぼそうとのはかりごとからえらび献上されたのが西施である。夫差は計略どおり西施にうつつの抜かし国を傾け、夫差に滅ばされる。
 <西湖>(せいこ)
<西湖>(せいこ)
東を街に接する。周囲は約15キロ。高見から見下ろす西湖も美しいし、湖岸から見る西湖も美しい。
古来、中国人が一生に一度は見てみたい風景として憧れてきた湖であり、これほど多くの詩人に詠まれた風景は他にはないであろう。
宋の時代、知事として滞在した蘇東坡は西湖をこう称えている。
水光瀲艷 晴偏好 (水光瀲艷 晴れてまさに好し)
山色空濛雨亦奇 (山の色、雲も濛として、雨もまた奇なり)
欲把西湖比西子(西湖を西施と比べんとせば)
淡粧濃抹総相宣(淡粧も濃抹もすべてあいよし)
 杭州の名物料理である東坡肉は、蘇東坡が杭州滞在中に考案した料理であるという。
湖には二つの堤がある。蘇堤と白堤。蘇堤は蘇東坡が県知事の時に築いた堤。南北に長さ2.8キロ。六つの橋が架かる。堤の柳が風に揺れ、リスが足下を走ったりする。
杭州の名物料理である東坡肉は、蘇東坡が杭州滞在中に考案した料理であるという。
湖には二つの堤がある。蘇堤と白堤。蘇堤は蘇東坡が県知事の時に築いた堤。南北に長さ2.8キロ。六つの橋が架かる。堤の柳が風に揺れ、リスが足下を走ったりする。
白堤は白居易が杭州の刺史を務めているときに修復をした堤である。
蘇堤の南の端に「花港観魚」という公園がある。南宋時代の官邸の跡を公園にしたもので、楼閣あり亭あり回廊ありののびのびとした風景が広がる。五百株の牡丹を擁する牡丹園と色とりどりの鯉が泳ぎ回る紅魚池がある。
 また、「花港観魚」の蘇堤を挟んだ反対側、西湖の中に浮かぶ島が三潭印月。島の南の湖中に三本の石の塔が立つ。塔心は空で丸い穴が開けてある。中秋の名月には、塔の中にロウソクの灯がともされ、薄い白紙を貼る。舟を浮かべると、塔の丸い灯りが湖面に映り、小さな月のようになる。「天には一つの明月、湖面には三つの影月」の奇観になる。宋の時代からの遊びと言われる。
また、「花港観魚」の蘇堤を挟んだ反対側、西湖の中に浮かぶ島が三潭印月。島の南の湖中に三本の石の塔が立つ。塔心は空で丸い穴が開けてある。中秋の名月には、塔の中にロウソクの灯がともされ、薄い白紙を貼る。舟を浮かべると、塔の丸い灯りが湖面に映り、小さな月のようになる。「天には一つの明月、湖面には三つの影月」の奇観になる。宋の時代からの遊びと言われる。
マルコポーロも『東方見聞録』のなかで西湖の船遊びに触れ、「この湖上の清遊ほど心楽しく愉快な遊楽はこの世にまたとないだろう。何しろこの湖水はキンサイ市(杭州のこと)の一辺に沿って延びているので、湖岸をうずめ尽くすかずかずの殿閣・寺院・道観、さては巨木森々たる庭園にいたるまで、すべてこの町のたたずまいや美観はこの遊覧船上から手に取るように眺めつくせるからである」(同前)。
<西冷印社>(せいれいいんしゃ)
 西湖の北にある島が弧山。西冷印社はその弧山にある。設立は清代の1904年。篆刻の研究を目的につくられた。「三老読字忌日碑」は後漢初年のものであり、浙江省では最も古い石碑である。
西湖の北にある島が弧山。西冷印社はその弧山にある。設立は清代の1904年。篆刻の研究を目的につくられた。「三老読字忌日碑」は後漢初年のものであり、浙江省では最も古い石碑である。
一般の旅行者には、石碑、拓本、書画、印材などのショッピングの場所となっている。
<霊隠寺>(れいいんじ)
 西湖から西へ数キロの山中にある。開山は326年。インドの僧・慧理による。慧理がここは仙霊が隠れているところだ、と言ったことから霊隠寺と名づけられた。
西湖から西へ数キロの山中にある。開山は326年。インドの僧・慧理による。慧理がここは仙霊が隠れているところだ、と言ったことから霊隠寺と名づけられた。
禅宗のお寺である。五代十国の時代(十世紀)には三千人の僧が修行をしていたという。
寺の南側の峰は飛来峰という。開山であるインドの僧・慧理がこの地を訪れたとき、「あれは天竺の霊鷲山の小峰ではないか。どうしてここに」と感嘆したことから飛来峰の名が付き、また、霊隠寺が建立されることになったという。そのした岩場に五代から宋にかけて石窟が造営され、石刻像が彫られている。青林洞、玉乳洞、龍泓洞などの石窟があり、そこに彫られた石仏の数は380におよぶ。このなかで有名なのは青林洞の弥勒仏像である。
<六和塔>(ろくわとう)
 杭州の南を流れる銭塘江に面して建つ。七層八角。高さは60メートル。
杭州の南を流れる銭塘江に面して建つ。七層八角。高さは60メートル。
北宋の時代の970年、呉越王・銭弘俶が銭塘江の高潮を鎮めるために建てた。
現在の塔は、南宋の1153年の再建である。上からは、銭塘江の流れを一望することができる。
銭塘江は長さ605キロの堂々たる大河、浙江、安徽、江西省境にある懐玉山脈に源を発し、桐江、富春江と名を変えながら浙江省の北部を東流し杭州湾に注ぐ。銭塘江とは、一般に、杭州から河口までを指す。
満潮時に潮流が津波のように川をさかのぼる海嘯とよばれる現象で知られる。河口がらっぱ状の形になっているために起こる現象である。最も激しいのは、毎年、旧暦の八月十八日前後。満潮の時に、三メートルを越える海水が河を時速25キロのスピードで遡る。大変な迫力である。
<梅家塢>(ばいかう)
 龍井茶の有名な産地。北京にある迎賓館である釣魚台で使われるお茶もここで産するお茶である。
龍井茶の有名な産地。北京にある迎賓館である釣魚台で使われるお茶もここで産するお茶である。
龍井茶は中国を代表する緑茶であるが、大きく四期に分けて収穫をする。清明節の前、清明節の後、四月、夏と秋。品質は、清明節の前を最高で、所謂新茶とは、このお茶を言う。
一面に茶葉かけが続き、農家の庭先で茶の葉を煎る光景もみられる。
《紹興》(しょうこう)
杭州から東南へ60キロ。紹興酒のふるさと、酒精の街である。街を縦横に水路が走り、舟が行き交う。水路の両岸には白壁の民家が建ち並ぶ。
春秋時代、呉と覇を競った越の国の都が置かれていたのがここ紹興である。
<魯迅紀念館>(ろじんきねんかん)
魯迅は紹興に生まれ紹興に育った。紀念館は魯迅故居、三昧書屋、陳列館からなる。
三昧書屋は、魯迅故居の筋向かいにあり、彼が十二歳から十七歳までかよった私塾である。魯迅が使っていた机が残されており、「早」と刻まれている。あるとき遅刻して叱られ、自分を戒めるために刻んだものと伝える。
魯迅(1881~1936)は、近代中国を代表するの文学者。
時代は清朝から中華民国に変わろうとしていた。列強諸外国の中国への侵出は日に日に激しさを増していた。そのなか、科挙制度を軸とした、体制に組み込まれた存在としての知識人にかわって、自立した知識人の誕生が求められていた。魯迅は、その時代的要請に誠実に応えようと生きた文学者であった。
紹興の没落地主の家に生まれ、進化論などの近代西洋思想の影響を受け、医者を志して日本の仙台に留学するが、滞在中に志を文学に転じる。
その間の事情を魯迅は、『吶喊』の「自序」や「藤野先生」でこう説明する。
留学先の仙台の学校で授業の合間などに幻灯をみた。日露戦争の時期であった。そこに、ロシア軍のスパイを働いた中国人と、その処刑される様子を周りで見物する中国人を見て、「あのことがあって以来、わたしは、医学など少しも大切なことでない、と考えるようになった。愚弱な国民は、たとい体格がどんなに健全で、どんなに長生きしようとも、せいぜい無意味な見せしめの材料と、その見物人になるだけではないか。病気したり死んだりする人間がたとい多かろうと、そんなことは不幸とまではいえぬのだ。されば、われわれのさいしょになすべき任務は、彼らの精神を改造するにある。そして、精神の改造に役立つものといえば、当時のわたしの考えでは、むろん文芸が第一だった」、と。
帰国後、「狂人日記」「孔乙己」「薬」「阿Q正伝」などを発表。自分たちの身に巣食う封建社会の負の意識を鋭く指摘、大きな影響を若い世代に与えた。
女子師範大学の学生運動の支持、ときの民国政府の民衆運動弾圧に対する激しい糾弾。これらを通じ、政府との軋轢は強まり、迫害をのがれて北京、アモイ、広東、上海と移り住む。
持病の結核に苦しみながらも、国民党政府と妥協することなく戦い続け、1936年、喘息により死亡。五十五歳であった。
紹興を舞台にした作品としては、「孔乙己」「故郷」などがある。
<八字橋>(はちじばし)
 紹興では、水路に架かる橋は下を舟が通るためアーチ型になっている。橋の上から眺めると、水路と舟と白壁の民家が美しい。八字橋の付近は清の時代の民家が残り、紹興の水路の風情を味わうに適した場所である。
紹興では、水路に架かる橋は下を舟が通るためアーチ型になっている。橋の上から眺めると、水路と舟と白壁の民家が美しい。八字橋の付近は清の時代の民家が残り、紹興の水路の風情を味わうに適した場所である。
ここでは東西の水路に南北の水路がぶつかりT字型になっている。ため橋の構造も北と東と西へ降りられるようになっている。それが八の字に見えることから八字橋の名が付いた。
<紹興酒工場>(しょうこうしゅこうじょう)
 市内には大小七十あまりの紹興酒工場がある。
市内には大小七十あまりの紹興酒工場がある。
中国の酒は、蒸留酒である白酒と、醸造酒である黄酒に大別される。白酒は強い酒で度数も38度から50度。脂っこい料理にある。一方、黄酒は12度から20度。老酒ともいう。江南の素材の味を生かした料理にはこちらが向いている。その黄酒の代表が紹興酒である。
紹興酒の材料は糯米、水には鑑湖の水を使う。鑑湖が水が酒造りに向いているのは、地下水に較べ鉱物の含有が少ないためだと言われる。
 <東湖>(とうこ)
<東湖>(とうこ)
街に東に位置する。青石の山であったが漢代から採石が続けられ、絶壁、洞窟ができた。そこに水を引き公園にしたもの。
ここでの楽しみは、足漕ぎ舟。紹興独特の舟で、竹で造った舟に黒い覆いを掛け、黒いフェルトの帽子をかぶった船頭が、足で漕ぎながら手で方向を調整する。
その足漕ぎ舟にのって園内を一周する。
<会稽山>(かいけいざん)
紹興は春秋時代の越国の都。呉と越の戦いのひとつの舞台である。会稽山は、越王・勾践と呉王・夫差の死闘の場所。「臥薪嘗胆」の故事はこう伝える。
紀元前四九六年。呉王・闔閭は兵を率いて越を攻めた。越王・勾践はこれを迎え撃ち呉軍を打ち破る。
闔閭はこの時に負った傷がもとで死ぬ。闔閭は死に際し太子の夫差を呼び、「勾践がおまえの父親を殺したことを忘れるな」、という。夫差は、復讐を忘れぬために「薪の上に寝、部屋の入り口に人を立たせておいて出入りのたびに、「夫差よ、越人がおまえの父親を殺したことを忘れたのか」と叫ばせた。
 越王勾践は、それを知ると、先手を打って呉を攻めた。夫差は精鋭を発し越を撃つ。越は敗れ、勾践は会稽山に包囲される。勾践は和を請い、勾践夫婦が夫差の奴婢となることを申し出る。
越王勾践は、それを知ると、先手を打って呉を攻めた。夫差は精鋭を発し越を撃つ。越は敗れ、勾践は会稽山に包囲される。勾践は和を請い、勾践夫婦が夫差の奴婢となることを申し出る。
呉の重臣・呉子胥はこの機に越を滅ぼすことを主張するが、夫差は越に買収された宰相のとりなしに従い和議を容れる。
勾践は国に帰ると、熊の肝を離さず、座するときにも臥するときにも立つときにもこれをなめ、苦さの中で「おまえは会稽の恥を忘れたか」と自らに言い聞かせた。
これが「臥薪嘗胆」、「会稽の恥」のいわれである。
結果は、それから二十年後、越王勾践は呉を破り、呉王夫差は自刃することになる。
会稽山は、紹興市の南に静かに聳えている。
<禹陵>(うりょう)
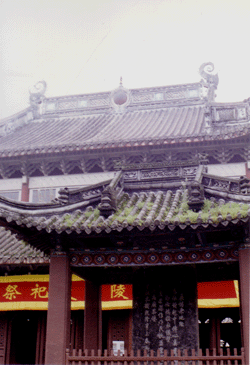 市の東南4キロ。禹は、中国古代の伝説上の王で、夏王朝の始祖とされる。儒教の聖人の一人。治水に功績があり、舜から禅譲によって帝位を受け、夏王朝をたてたという。
市の東南4キロ。禹は、中国古代の伝説上の王で、夏王朝の始祖とされる。儒教の聖人の一人。治水に功績があり、舜から禅譲によって帝位を受け、夏王朝をたてたという。
夏王朝を建てたのち、各地を巡遊しながらこの地に至り崩じたとの言い伝えから陵が造られたようである。
『史記』の「夏本紀」にも、「帝禹が東方に巡狩して会稽に行ったとき崩じ」とある。
<蘭亭>(らんてい)
紹興市の西南14キロ。東晋の書家・王羲之が「蘭亭序」を書いた地である。
西暦353年。三月三日。王羲之は当地の名士四十一名と蘭亭に会し曲水の宴を催した。曲水の宴というのは、曲水のほとりに参会者が座り、上流から流される酒杯が自分の前を通り過ぎる前に詩歌を作る、という遊びである。終わって宴を設け、それぞれの詩歌を披露した。日本にも伝わり、平安時代、宮中でやはり、三月三日の上巳の節句に行われた。
 蘭亭序とは、この時の会で成った詩集に王羲之が付けた序文である。当時より行書の傑作中の傑作と言われ、広く手本とされた。原文は、その後、唐の太宗・李世民の手に渡るところとなったが、李世民はこれを深く愛し、逝去の際、太宗とともに埋葬させた、いわれる。
蘭亭序とは、この時の会で成った詩集に王羲之が付けた序文である。当時より行書の傑作中の傑作と言われ、広く手本とされた。原文は、その後、唐の太宗・李世民の手に渡るところとなったが、李世民はこれを深く愛し、逝去の際、太宗とともに埋葬させた、いわれる。
御碑亭の「蘭亭」の字は清代康煕帝が書いたもの。
↑ ページのトップへ
《寧波》(にんぽ)
古くは明州とよばれた。唐代は中国のもっとも重要な港湾都市として繁栄し、日本の遣唐使船のほとんどは先ずここに到着。その後、大運河を経由して長安などにむかった。
 日本の室町時代、第三代将軍足利義満は,室町幕府の財政難を打開するために対明貿易を始める。明は朝貢の形式で入港を認めた。つまり、日本が朝貢として品物を中国へ差し出す、それに対する答礼という形でその何倍もの品物を下賜する。
日本の室町時代、第三代将軍足利義満は,室町幕府の財政難を打開するために対明貿易を始める。明は朝貢の形式で入港を認めた。つまり、日本が朝貢として品物を中国へ差し出す、それに対する答礼という形でその何倍もの品物を下賜する。
室町幕府としては屈辱的ではあったが、莫大な利益があり、当時の窮迫した財政事情から止めるわけにはいかなかった。
明側からみた第一の狙いは倭寇の取り締まりであった。そのため、倭寇と区別するため正式な遣明船には勘合符を持参させた。そのためこの取引を勘合貿易という。日本からは刀剣・扇・びょうぶなどが輸出され、明からは銅銭・絹織物・書画などが輸入された。
この勘合貿易の明の窓口が寧波であった。
季節風に対する理解が深まっており、春と秋に吹く東北の風に乗って大陸へ行く。そして、五月過ぎの夏の風に乗って帰って来るという航海技術が開発され、安全に航行が出来るようになっていたという。
<天一閣>(てんいちかく)
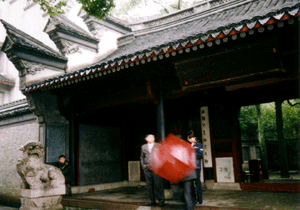 中国に現存する最も古い書庫。建てられたのは1561年。建てたのは兵部右侍郎の範欽。範欽は書の蒐集につとめ集めた本は七万巻を越える。
中国に現存する最も古い書庫。建てられたのは1561年。建てたのは兵部右侍郎の範欽。範欽は書の蒐集につとめ集めた本は七万巻を越える。
蔵書の多くは明代の刊本と写本であるが、歴史的資料として注目されているのは明代に出版された明刻版の地方志の蒐集である。
 蔵書館の前に掘られた池は天一池。蔵書を火災から守るための用水として掘られたものだが、周りに配された建築群とともに庭園芸術のひとつの範となっている。
蔵書館の前に掘られた池は天一池。蔵書を火災から守るための用水として掘られたものだが、周りに配された建築群とともに庭園芸術のひとつの範となっている。
ここに身を置くと、交易の港として栄えた寧波という街で、当時の知識人が憧れた空間の形、そこに流れるべき時間の形、というものが想像できるのである。
また、2001年、天一閣の敷地の中に『麻雀陳列館』が新設され、道具やルールの変遷が説明されている。今の麻雀牌の原形をつくったのが陳魚門という19世紀の寧波の名士であったとされることからである。
<慶安会館>(けいあんかいかん)
 甬江と奉化江との交わるところ、水運の要所に建つ。清代1853年、江南第一天後宮と江南第一会館を併せて、慶安会館として建てたもの。前者は媽祖廟であり、後者は船員の倶楽部である。
甬江と奉化江との交わるところ、水運の要所に建つ。清代1853年、江南第一天後宮と江南第一会館を併せて、慶安会館として建てたもの。前者は媽祖廟であり、後者は船員の倶楽部である。
媽祖は航海の安全を守るという女の神様で、中国での信仰は篤く、福建、広東などの港町には大抵おおきな媽祖廟が造られている。始まりは11世紀とされる。
娯楽の場としての倶楽部と安全祈願の場としての媽祖廟がひとつのセットとして用意されていることは興味深い。
寧波が果たしてきた海外との交易・交流の歴史を示す図やイラスト展示物が展示されている。
<道元禅師入宋記念碑>(どうげんぜんしにゅうそうきねんひ)
道元の入宋は1223年。その上陸地点に道元禅師入宋記念碑が造られている。
帰国後、永平寺を創建し、日本曹洞宗の開祖となった。臨済宗の公案を中心とした禅に対し、悟りを求めたり想念をはたらかすことなく、ひたすら座禅することを唱えた只管打坐の禅風で知られる。日本の禅宗に決定的な影響を与えたのが道元であるが、その道元に、これまた、決定的な影響を与えたのがこの地での修行であった。
 その第一歩を記したのが、この辺りであるが、道元自身がここでの経験談を語っている。
その第一歩を記したのが、この辺りであるが、道元自身がここでの経験談を語っている。
船は着いたがまだ上陸が許されない。そんなときのことだ。阿育王山の典座和尚がひとり、日本船入港ときいて、椎茸を買いに来た。典座とは寺の食事をまかなう役職である。聞いてみると、昼食後、5里以上もある道を歩いてきて、買出しがすめば、またすぐ帰るのだという。それを聞いて道元は尋ねる。「どうして典座の職などしているのですか?」。坐禅とか読経とかの修行に専念すべきではないのか、と。
典座は答える。
「外国のお客人よ、あなたはまだ仏道のなんたるかがわかっていない。文字の何たるかもわかっていない」
道元はショックを受け、典座を引き留めようとする。大きなお寺、あなたがいなくともる、他にも食事の用意をする人はいるでしょう、と。
典座は答える。
「これは修行なのです。どうして他人に任せることができましょう」。
道元はのちに言う。「山僧(道元)いささか文字を知り、弁道を知るを了ずることはすなわち彼の典座の大恩なり」(「典座教訓」)
行住坐臥、すべて、仏法でないものはない。道元生涯の修行・勉学の結論のひとつであるが、それを意識する契機となったのが、この港における典座との出会いであった。
<阿育王寺>(あいくおうじ)
寧波市の東16キロ。禅宗の寺で中華五山のひとつである。他の四つは、径山寺(余杭)、霊隠寺(杭州)、浄慈寺(杭州)、天童寺(寧波)である。
阿育王とはインドのアショカ王のこと。在位は紀元前268~232年頃で、マウリヤ王朝第三代の王である。古代インドにおける統一国家建設の偉業を果たしたが、その過程で経てきた戦争の悲惨な結果を悔い仏教に深く帰依する。
さて、彼は、仏教を広めるための一つの方策として、釈迦入滅時に建立された仏舎利塔を開き、仏舎利の広く分配することを思い立った。こうして、仏舎利を8万4千に分けた、という。
そのひとつが、ここにある。その仏舎利を納める塔が舎利宝塔である。
<天童寺>(てんどうじ)
 寧波の東30キロ。禅宗の寺で中華五山のひとつ。「天下禅宗五山の第二」と称され、中国仏教史のなかで果たしてきた役割は大きい。
寧波の東30キロ。禅宗の寺で中華五山のひとつ。「天下禅宗五山の第二」と称され、中国仏教史のなかで果たしてきた役割は大きい。
西暦300年に晋の義興がここに庵を結んだのを嚆矢とする。寺の建設は唐代の732年。
十三世紀、道元はここに修行し帰国後日本曹洞宗を創立。日本臨済宗の開祖・栄西も天童寺で修行をしていた。
時代が少しくだった15世紀、雪舟も、この寺に滞在しており、その時、「四明天童寺第一座」という禅僧としての高い役位に補せられている。このように、日本との因縁浅からぬ寺であり、日本仏教に与えた影響も大きい。
太白山の鬱蒼として緑の中に、大雄宝殿、天王殿、仏殿、法堂、玉仏殿、鐘楼など二十余りの大きな建築が軒を連ねる。
道元は入宋後修行に励みまた幾つかの寺を遍歴するが悟りの自覚を得ることができない。そんな折り、天童寺の新しい住持に如浄禅師が就いたことを聞く。そこで再び天童寺に帰錫するが、この如浄禅師との出会いが、その後の道元を決めることになる。
 初めて如浄禅師にまみえたときの感動を、「まのあたり先師をみる、これ人にあふなり」とのちに正法眼蔵に書き記す。昼夜を問わず如浄禅師の傍を離れず薫陶を受け精進を重ね、そしてある日、大悟する。
初めて如浄禅師にまみえたときの感動を、「まのあたり先師をみる、これ人にあふなり」とのちに正法眼蔵に書き記す。昼夜を問わず如浄禅師の傍を離れず薫陶を受け精進を重ね、そしてある日、大悟する。
ある日の早暁坐禅の時、一人の僧がいねむりをした。これを見た如浄禅師は一喝した。「参禅は身心脱落である。いねむりするとは何事だ」。この一喝に、突如、身心脱落の境地を得た、という。
↑ ページのトップへ
《天台山》(てんだいさん)
浙江省の紹興から寧波の南に峰を連ねる山である。最も高いのは華頂山の1138メートル。四川省の峨眉山、山西省の五台山とならび中国仏教三大霊場のひとつとされる。
古来名山とされ、道教の霊山とされてきたが、575年、仏僧智顗が入山して天台宗を開き、根本道場としてから、仏教の中心地となる。
<国清寺>(こくせいじ)
天台山を代表する寺院は国清寺。天台山の南麓にある。創建は隋代の598年。
伽藍は、東中西の三列に配置されている。中の線には、弥勒殿、天王殿、大雄宝殿。東の線には斎堂、方丈楼、迎塔楼、修竹軒、禅堂、静観堂。西の線には、安養堂、観音堂、妙法堂などが。壮大な伽藍であるが、これらの建物を回廊で繋いでいる。回廊の長さは1800メートル。
日本の最澄は、唐代の804年、ここ国清寺で天台宗を学び、帰国後日本天台宗を開く。
↑ ページのトップへ
《普陀山》(ふださん)
杭州湾に浮かぶのは舟山群島。その一つに普陀山がある。寧波からホーバークラフトで二時間。周囲22キロメートルの小島であるが、五台山、峨眉山、九華山とならぶ中国仏教四大聖山の一つである。
観音菩薩の霊場である。『華厳経』に、観音菩薩の住む場所として「ポータラカ」という地名が出てくる。南瞻部洲(インド)だという。このサンスクリットの「ポータラカ」を中国では「普陀」と漢字を当てた。チベットでは「ポタラ」とし、日本では「補陀洛」とした。
漢の時代には道教の神仙郷としての信仰を集めたが、仏教が盛んになるのは唐代以降である。特に、宋代には全山を禅宗に統合して大々的な仏教聖地とした。
清代、一時は荒廃したが、康煕帝が杭州に行幸の際、普陀山再建の費用を寄付し、また、前寺に「普済群霊」、後寺に「天花法雨」の額を下賜した。以降、普済禅寺、法雨禅寺の呼称で呼ばれるようになったという。
 <普済寺>(ふさいじ)
<普済寺>(ふさいじ)
小さなに島に三十をこえる寺院があるが、その中でも最も大きな寺である。創建は1080年。宋の朝廷から「宝陀観音寺」の名を賜り観音道場としたのが始まり。山門から天王殿、大円通殿、法堂、法丈殿、功徳殿と続く。本尊は大円通殿に安置する観音坐像。
<法雨寺>(ほううじ)
 普済寺の北。普陀山では普済寺に次ぐ規模の寺。緑濃い山に向かって伽藍がつま先上がりに続く。天王殿、玉仏殿、九龍観音殿、大雄宝殿、方丈殿と並ぶ。
普済寺の北。普陀山では普済寺に次ぐ規模の寺。緑濃い山に向かって伽藍がつま先上がりに続く。天王殿、玉仏殿、九龍観音殿、大雄宝殿、方丈殿と並ぶ。
九龍観音殿の天井には九つの龍の彫刻が施されている。これは、清代、康煕帝がこの寺に下賜したもの。
創建は1580年だが、現存する建物はみな清代以降の再建。
<不肯去観音院>(ふこうきょかんのんいん)
 十世紀、五代の梁の時代、日本僧の慧萼が山西省の五台山で銅製の観音像を拝領した。寧波から帰国の船に乗るが、普陀山にさしかかると海面に幾つもの蓮の花が現れ、船が動かなくなった。慧萼は観音様が中国を離れたくないのだ(不肯去)と考え、島民の家に像を安置して「不肯去観音院」と名づけたという。
十世紀、五代の梁の時代、日本僧の慧萼が山西省の五台山で銅製の観音像を拝領した。寧波から帰国の船に乗るが、普陀山にさしかかると海面に幾つもの蓮の花が現れ、船が動かなくなった。慧萼は観音様が中国を離れたくないのだ(不肯去)と考え、島民の家に像を安置して「不肯去観音院」と名づけたという。
↑ ページのトップへ
|