《ウルムチ》(烏魯木斉)
ウルムチは新彊ウイグル自治区の区都。
新彊ウイグル自治区の略称は「新」。中国の西北部に位置し、所謂「西域」に属する。中国の支配権が及ぶようになったのは漢。武帝の時代、西域都護府を置いてからである。唐代には北庭都護府と安西都護府が置かれた。新彊と呼ばれるようになったのは、清朝の光緒年間に新彊省となってから。新彊ウイグル自治区の成立は1955年。
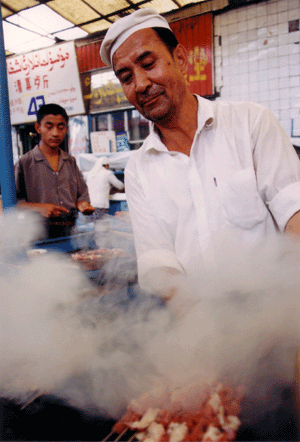 中国31の省・自治区・直轄市のなかで最も面積が広く、全国の六分の一を占め、日本全土の四倍をこえる。
中国31の省・自治区・直轄市のなかで最も面積が広く、全国の六分の一を占め、日本全土の四倍をこえる。
一番多い民族はウイグル族。人口の半分を超える。他には、漢族以外、ハザク、回、キルギス、蒙古、シボ、タジク、ダフル、ウズベク、満州、タタール、スラブの11の少数民族が暮らす。
自治区全体が大陸性気候に属し、年間降水量が25-100㎜で乾燥をしている。また、一年を通じての気温の変化は激しく、夏は35度をこえる日が続く一方、冬には寒さが厳しい。同時に、一日の中でも温寒の差は大きく「朝には綿入れ、昼には半袖、夜は火鉢を抱えてスイカを食べる」などと表現される。
 漢王朝以来、東西の交通路が開かれ、人や物の往来のみならず、宗教、文化の通り道となった。そのため多くの史跡を残す。
ウルムチは比較的新しい街で、18世紀の後半、清朝のジュンガル部遠征以降、ここ(当時の地名は迪化)を西域管轄の中心にしてからのことである。上に述べた新彊省の成立はこのことをいい、1884年のことである。
漢王朝以来、東西の交通路が開かれ、人や物の往来のみならず、宗教、文化の通り道となった。そのため多くの史跡を残す。
ウルムチは比較的新しい街で、18世紀の後半、清朝のジュンガル部遠征以降、ここ(当時の地名は迪化)を西域管轄の中心にしてからのことである。上に述べた新彊省の成立はこのことをいい、1884年のことである。
ウルムチとはモンゴル語で「美しい牧場」の意味であるが、ウルムチと名付けられたのは、1952年のことである。
また、ウルムチはしばしば、「海から最も遠い町」などと言われる。東の黄海からも南のベンガル湾からも北のカラ海からも西のアラビア海、バルト海からも2300キロ以上離れている内陸の中の内陸である。
<新彊ウイグル自治区博物館>(しんきょうウイグルじちくはくぶつかん)
ウルムチ市西北路にある。新彊ウイグル自治区で最大の博物館。建物自体にウイグルの特徴を持たせている。屋根は、緑色の円形ドーム。正面の外壁にも、内壁にも白い石膏で民族的な装飾が施されている。
展示は、「歴史文物陳列室」と「民族民俗陳列室」と「ミイラ陳列室」に分かれている。
特に印象に残るのは、「ミイラ陳列室」。楼蘭、トルファンなどから出土されたミイラが十体ほど展示してある。なかでも有名なのが楼蘭の美女。
楼蘭は、シルクロード上のオアシス国家。史書へ登場するのは紀元前一世紀。匈奴の王が漢の皇帝へ宛てた書簡の中で、自分が支配する西域の国々の中のひとつとして言及しているのが肇である。その後、最盛期を迎えるのは三世紀。西域南道の東部を支配し、東西交易の要衝として栄える。
やがて中国の王朝の支配を受けることになるが、七世紀を最後に全ての記録から姿を消してしまう。
その楼蘭が再び、人々の前に姿を現したのは、二十世紀。スウェーデンの探検家・ヘディンにより遺跡が発見されてからである。
「楼蘭の美女」とは1980年に楼蘭の遺跡から発掘された女性のミイラである。埋葬の時期は紀元前1000年。45歳、157cm、O型。顎のやや尖った細面の顔だちで大きな眼をもつ。髪の毛は明るいブラウン。人種はヨーロッパ系。足には鹿の皮の靴を履き、頭には、鳥の羽根をさしたフェルトの帽子をかぶっている。
「民族民俗展」では、ウイグル族のほかハザク、キルギスなどの民族の住居、衣服、生活様式などを示す展示がされている。特に衣服については、それぞれの民族が持つそれぞれの色彩感覚が鮮やかに表現されていて興味深い。
 <紅山>(こうざん)
<紅山>(こうざん)
市の中心部にそびえる。市のシンボル的存在。岩肌が赤褐色をしているので紅山という。最も高いところで標高910メートル。登ると街全体を眺望できる。
頂上に玉皇閣と高さ八メートルの鎮龍塔がある。鎮龍塔は氾濫を繰り返すウルムチ河の龍を鎮めるために建てられた。
<バザール>
 西域の街の楽しみとしてバザール見学がある。長い顎髭に男たち、鮮やかな民族衣装をまとった女たちを見ているだけでも楽しい。
西域の街の楽しみとしてバザール見学がある。長い顎髭に男たち、鮮やかな民族衣装をまとった女たちを見ているだけでも楽しい。
同時に、市場に所狭しと並べられた品々。麻の袋に詰められた色とりどりの香辛料。ナイフ。楽器。丸ごと裸で吊された羊。
西域の活気と異国情緒が私たちを包む。
<ウラノール古城>(鳥拉泊古城)
ウルムチの市街の南10キロ。唐代の輪台城とされる。輪台城とは、異民族との戦いの最前線であった城である。輪台城に宿営してい詩人・岑参はこう詠む。
平沙莽莽黄入天 (沙漠はもうもうとして天は黄の色に染まる)
輪台九月夜風吼 (輪台の九月 夜に風は吼える)
一川砕石大如斗 (川じゅうに砕けた石があるが大きいものは一斗はありそうだ)
随風満地石乱走 (風が吹けば石という石が乱れ走る)
城壁が残っており、東西480メートル、南北550メートル、高さは4メートル。
城内からは、陶罐、蓮花紋様の方磚、壺、古銭などを出土している。唐に始まり、元の時代まで使われていたと考えられている。
ウラノール古城の東北二キロ、ウラノール・ダムの南斜面で古墳が発見された。1983年に発掘調査が行われているが、発掘されたのは46基。石棺墓と土坑墓がある。金製の耳飾り、銅鏡、陶器、小鉄器などが出土している。時代は、紀元前二、三世紀。サルマタイ系車師人のものと考えられている。
<天池>(てんち)
ウルムチの東110キロ。ボゴダ峰の中腹にある。ボゴダ峰の標高は5445メートル、また、天池の標高は1980メートル。水の色は青々としていて、万年雪を戴くボゴダ峰と、それに抱かれるように広がる湖の取り合わせには鮮烈な美しさがある。
中国の神話にしばしば登場する女神に西王母がいる。住処は崑崙山。伝説に、周の穆王が西に巡狩した時、西王母は瑶池で宴を開きこれをもてなした、とあるが、地元では、その瑶池が天池であると言う。
辺りは深い森が続くが、森の中に点在する草原にはカザフ族のパオがある。
<南山牧場>(なんざんぼくじょう)
ウルムチから南へ75キロ。天山山脈の北麓に広がる高原が南山である。広々とした草原とそれを横切る幾筋もの渓流がある。渓流は天山の雪解け水。
カザフ族の放牧地である。草をはむ羊の群れと、馬に乗りそれを追う若者。
遊牧の世界にしばし浸ることが出来る。
南山で最も美しい風景と言われるのは、西白楊溝。水量ゆたかな滝がある。高さ40メートル、幅2メートル。緑の木々を縫うように一筋の白滝が断崖をなだれ落ちる。
<アラ溝木槨墓>(なんざんぼくじょう)
アラ溝は地名。槨は棺の外側を覆う外棺のこと。竪穴式の墓室があり、そこに松の木で組まれた槨があり、そのなかに木棺がある。
場所は、ウルムチし南山区。1976年から発掘が始められ85の墓が発掘された。そのうち木槨墓は六基。一~二名ずつ合葬されている。副葬品には陶器、金器、銅器、漆器、絹織物、真珠、羊骨などがあるが、そのうち虎の紋様の入った金牌、獅子型の金箔の飾りなど獣面紋様の装身具は、紀元前三世紀から紀元四世紀にかけスキタイに代わって南ロシアを支配したイラン系遊牧民であるサルマタイ独特の動物紋様との共通性がみられ、関係が示される。
また、同時に鳳凰紋様の絹の刺繍も発掘されており、中国との関係も明らかである。
炭素一四の測定から中国の戦国時代から前漢時代のものだとされている。また、埋葬されているのは、民族的には、当時トルファン盆地に勢力を張った車師人ではないかと想像されている。
現在、墓は、保護のため埋め戻されている。
↑ ページのトップへ
《トルファン》(吐魯番)
 天山山脈の南東麓、トルファン盆地の中央にあるにあるオアシス都市。トルファンはウイグル語で「くぼんだ土地」の意。市の南にあるアイディン湖は、湖面が標高マイナス154メートル、世界で二番目に低い所にある湖である。一番は死海でマイナス399メートル。
天山山脈の南東麓、トルファン盆地の中央にあるにあるオアシス都市。トルファンはウイグル語で「くぼんだ土地」の意。市の南にあるアイディン湖は、湖面が標高マイナス154メートル、世界で二番目に低い所にある湖である。一番は死海でマイナス399メートル。
古来、「火州」と呼ばれ、夏の平均最高気温は38度をこえる。一方、降水量は年間で25ミリと極端に少ない。
 北へ向かえば天山の北麓に、南に向かえば天山南路。その地理的な位置より、古くからシルクロード上最も重要な拠点のひとつであった。中国の前漢の時代には交河故城を王城として車師前国が栄えていた。玄奘三蔵法師がインドへ向かう途中立ち寄った時に栄えていたのは高昌国。唐は、その高昌国を滅ばしここに安西都護府を置く。その後、チベット、西ウイグル国、モンゴル、東チャガタイ=ハン国、カシュガル=ハン国、ジュンガル部が支配するところとなった。
北へ向かえば天山の北麓に、南に向かえば天山南路。その地理的な位置より、古くからシルクロード上最も重要な拠点のひとつであった。中国の前漢の時代には交河故城を王城として車師前国が栄えていた。玄奘三蔵法師がインドへ向かう途中立ち寄った時に栄えていたのは高昌国。唐は、その高昌国を滅ばしここに安西都護府を置く。その後、チベット、西ウイグル国、モンゴル、東チャガタイ=ハン国、カシュガル=ハン国、ジュンガル部が支配するところとなった。
<トルファン博物館>
 二階建ての建物。規模は大きくないが、出土品、ミイラなどにシルクロードの要衝としての歴史を感じさせる。
二階建ての建物。規模は大きくないが、出土品、ミイラなどにシルクロードの要衝としての歴史を感じさせる。
一階には高昌故城、交河故城、ベゼクリク千仏堂、アスターナ古墳群などから出土した石器、木器、陶器、絹、麻や毛の織物、墓誌などが展示されている。
二階は、アスターナ古墳群などから発掘されたミイラが展示されている。
<カレーズ博物館>
「カレーズ」はペルシャ語。「掘って水を通す設備」。山麓に地下水を掘り当て、その水を村まで引いてくる。引いてくる方法は、二、三十メートルごとに竪穴を掘り、それを横穴で繋いで水を通してくる。
井戸はもっとも深いものでは70メートル近くにもに達する。また長さは、普通は3キロ程度、もっとも長いもので10キロである。
トルファンには千二百本のカレーズがある。これにより、天山の雪解け水の伏流を引いてきている。これにより、中国で一二を争う乾燥地帯であるにもかかわらず、村の水路には水が溢れ、ポプラの並木が葉を風に揺らせながら日陰を作っている。トルファンは葡萄の産地として名高いが、それを可能にしているのもカレーズである。
<葡萄溝>(ぶどうこう)
 市街から東北へ10キロ。火焔山の西側の渓谷を利用して葡萄の栽培が行われている。幅1キロ、長さ9キロ。
市街から東北へ10キロ。火焔山の西側の渓谷を利用して葡萄の栽培が行われている。幅1キロ、長さ9キロ。
葡萄栽培の歴史は古く、5~6世紀には麹氏高昌国で葡萄が栽培されていたと史書に記されている。
トルファンで名高いのは「馬の乳房」と呼ばれる細長い薄緑の葡萄。乾しぶどうにもされる。
<蘇公塔>(そこうとう)
市の中心部から東へ2キロ。イスラム建築の尖塔である。
1779年に時のトルファン郡王のスレイマン(蘇来満)が父親の(エミン)額敏を記念するため建てた。別名、額敏塔ともいう。
高さ44メートル。外壁は煉瓦の組み合わせて様々の紋様を描き出している。塔内も材を使わずに煉瓦を積みあげた螺旋形の支柱で塔を支えている。
塔の下には教堂が建てられている。また、漢文とチャガタイ文の二言語で書かれ建塔の碑もある。
<高昌故城>(こうしょうこじょう)
 トルファンの市街地から東へ40キロのところにある。前漢はここに高昌壁をつくり漢人を入植させた。その後、五世紀から七世紀にかけ、漢人の麹氏が建てた高昌国の王城として栄えた。
トルファンの市街地から東へ40キロのところにある。前漢はここに高昌壁をつくり漢人を入植させた。その後、五世紀から七世紀にかけ、漢人の麹氏が建てた高昌国の王城として栄えた。
東西1.4キロ、南北1.5キロ。建物はすべて日干し煉瓦で造られていた。それが、風化を受け、ほとんど廃墟となって広がっている。
それでも、王城、景教寺院、マニ教寺院、仏教寺院などの遺跡を判別できる。
 現在我々が目にする高昌故城は、麹文泰が建てたものと言われるが、玄奘三蔵をこの地へ招聘したのがその麹文泰である。628年のこと。玄奘はお礼に一ヶ月、仏教の講義をしたという。玄奘が、インドからの帰り、再訪しようとしたが、その時には唐によって滅ぼされた後であった。高昌国の滅亡は640年。玄奘の長安帰着は645年であった。
現在我々が目にする高昌故城は、麹文泰が建てたものと言われるが、玄奘三蔵をこの地へ招聘したのがその麹文泰である。628年のこと。玄奘はお礼に一ヶ月、仏教の講義をしたという。玄奘が、インドからの帰り、再訪しようとしたが、その時には唐によって滅ぼされた後であった。高昌国の滅亡は640年。玄奘の長安帰着は645年であった。
唐は高昌国を滅ぼした後、安西都護符を、交河故城におくが、更にその後はウイグルの高昌国の王都として栄えた。廃されたのは明代前期。
<アスターナ古墳群>
トルファン市の市街の東南40キロ。高昌故城の北西4キロ。4世紀から7世紀にかけてこの地に栄えた麹氏高昌国の古墳群。墓の数は五百。葬られているのは、多くは漢族の豪族。家族ごとに埋葬されている。
 遺体はミイラ化し、同時に、副葬された埋葬品も保存状態はよい。絹織物、陶器、木器、貨幣、墓誌、文書類が発掘されている。なかで有名なものは、絹本の伏羲女蝸図、舞楽図、囲棋仕女図、牧馬図、樹下美人図、樹下人物図などである。
遺体はミイラ化し、同時に、副葬された埋葬品も保存状態はよい。絹織物、陶器、木器、貨幣、墓誌、文書類が発掘されている。なかで有名なものは、絹本の伏羲女蝸図、舞楽図、囲棋仕女図、牧馬図、樹下美人図、樹下人物図などである。
なお、アスターナはウイグル語で「首府」の意。
<火焔山>(かえんざん)
 トルファン盆地の中部に横たわる岩山。夏の強い光が当たると燃えるように赤くなる。地元の人は、キジル・タグ(赤い山)と呼ぶ。
トルファン盆地の中部に横たわる岩山。夏の強い光が当たると燃えるように赤くなる。地元の人は、キジル・タグ(赤い山)と呼ぶ。
色が赤いばかりでなく、地質学では、地殻にはたらく力によって地層が波状に押し曲げられることを褶曲と言うがその褶曲運動により、山肌に縦に無数のひだが入っていて、赤い炎のように見える。
東西100キロ、南北10キロの、平均海抜約500メートルである。
『西遊記』の「唐三蔵火焔山に阻まれること 孫行者芭蕉扇を奪いとること」の一段が、ここを舞台にしている。
三蔵が土地の老人に問う。
「ご当地は秋だというのに、どうしてこんなに暑いのでしょうか」。
 老人、答えて曰く、「この地は火焔山と申しましてな、春も秋もござらぬ。四季を通じて暑いのですじゃ」。更に続けて、「ところがあたり一面、火がぼうぼうで、草一本生えておりませんな。そこを通ろうものなら、よしんば銅のあたまに鉄のからだを持っていたとしても、どろどろに溶けて汁になってしまいますじゃ」。(括弧内は中野美代子訳『西遊記』岩波文庫からの引用)
老人、答えて曰く、「この地は火焔山と申しましてな、春も秋もござらぬ。四季を通じて暑いのですじゃ」。更に続けて、「ところがあたり一面、火がぼうぼうで、草一本生えておりませんな。そこを通ろうものなら、よしんば銅のあたまに鉄のからだを持っていたとしても、どろどろに溶けて汁になってしまいますじゃ」。(括弧内は中野美代子訳『西遊記』岩波文庫からの引用)
そこで、燃える火焔山を過ぎるために、「ひとつ煽げば火が消える、ふたつ煽げば風おこる、みっつ煽げば雨が降る」という芭蕉扇を鉄扇公主から奪う話である。
また、唐の詩人・岑参は「火山を経る」でこう詠う。
火山 今始めて見る
突兀(トッコツ)たり 蒲昌の東
赤焔 虜雲を焼き
焔氛 塞空を蒸す
知らず 陰陽の炭
何ぞ 独り此の中に燃ゆるや
我来るは厳冬の時なるに
山下に炎風多し
人馬 尽く汗流る
孰(タレ)か知らん造化の功
<アイディン湖>(艾丁湖)
トルファン盆地の南部にある。トルファン市からは南へ40キロ。アイディンはウイグル語で「月光」の意。湖上や湖岸が塩の結晶で白く輝いていることから付けられた。
海抜はマイナス154メートル。中国でもっとも低い地点である。
春は雪溶水が流れこむために水をたたえるが、夏から秋にかけては、強い日ざしのために湖水は蒸発し、湖底をあらわす。
<ベゼクリク千仏洞>
 トルファン市から東へ60キロ。火焔山北麓のムルトゥク河の断崖に掘られた石窟寺院。幅400メートル。現存するのは64窟。開削は六世紀の麹氏高昌国に始まる。最盛期は十世紀、トルファンはウイグル高昌国の中心であったが、その頃のウイグル人はまだイスラム化しておらず仏教を信奉していた。そのウイグル人によって造られた。
トルファン市から東へ60キロ。火焔山北麓のムルトゥク河の断崖に掘られた石窟寺院。幅400メートル。現存するのは64窟。開削は六世紀の麹氏高昌国に始まる。最盛期は十世紀、トルファンはウイグル高昌国の中心であったが、その頃のウイグル人はまだイスラム化しておらず仏教を信奉していた。そのウイグル人によって造られた。
ウイグル人は九世紀の半ばに草原地帯からトルファン盆地に移住してきたが、それで、彼らは様々な宗教に出会った。仏教、マニ教、ネトリウス派キリスト教、ゾロアスター教など。そのなかで最初にから彼らと接触のあったソクド人商人の奉じていたのがマニ教であったからである。その後、時が経つにつれ、仏教やキリスト教に改宗するものが出てくることになる。
ベゼクリク千仏洞のなかに、37窟など、マニ教の寺として造られながら仏教に改変したものが見られるのはそういった事情による。
ウイグル人のイスラム化は、地域により、年代はかなりずれるとされている。ホータン地区で11世紀、クチャは12世紀、トルファンは最も遅く15世紀といわれている。
ベゼクリクはウイグル語で「装飾された家」。華やかな壁画に飾られた窟が多い。ただし、またそれ故に、スタインなどの外国の探検家に壁を切り取られ持ち去られることにもなった。
残された中で名高いのは第39窟の「各国王子挙哀図」。挙哀とは、葬儀のさいに遺族などが号泣して悲しみを表すことであるが、この図には西域のさまざまな民族の姿、衣装、髪飾りなどが描かれていて、当時の風俗、生活を偲ばせる。
<交河故城>(こうがこじょう)
 トルファンの街から西へ10キロ。二本の河の交差するところにあるので交河故城という。中国の漢代の車師前王国の治所の所在地とされる。今から2200年ほど前のことになる。
トルファンの街から西へ10キロ。二本の河の交差するところにあるので交河故城という。中国の漢代の車師前王国の治所の所在地とされる。今から2200年ほど前のことになる。
高昌故城が漢以降この地に進出した漢人の住処であったのに対し、交河故城は騎馬民族と思われる車師人の古くからの住処であった。ふたつの城は、70キロ離れながらそれぞれ独自の文化を保持していた。
車師前王国の滅亡は紀元450年。その後は、交河故城も漢人の支配するところとなった。
麹氏高昌国の時代には、高昌故城の副都的な存在で、交河郡城と呼ばれた。
その後、唐は、麹氏高昌国を滅ぼすと 安西都護府を置いたがその在所が交河故城であった。
現存するのは唐の時代と、それ以降のもの。東西1000メートル、南北300メートルの長方形をなし、東と南に城門がある。城壁はない。城内南部に幅3メートル、長さ350メートルの大通りが南北に貫き、その両側に崩れ落ちながらも土の建物群が残っている。その大通りを軸に三つに地区に分かれていたと考えられている。西北区は寺廟地区。寺の遺構や仏塔がある。東北区は居住区。小型の建物が並ぶ。東南区は大きな建物が多く、役所区であったとされる。また、大通りの北の先に版築で築いた仏教寺院があり、搭の上に置かれた仏龕に仏像が残っている。
これらすべてが土で造られたものである。
↑ ページのトップへ
《コルラ》(庫爾勒)
コルラは天山山脈の南麓、タクラマカン砂漠の北縁に位置し、孔雀河が市内を流れる。孔雀河はタリム河の支流、かつては楼蘭王国を潤していた河でもある。
そういう位置にあり、古くから、東にトルファン、西にクチャ、南に楼蘭、その三つの主要オアシスをを結ぶ要衝の地であった。
近年はタクラマカン砂漠の石油発掘の前線基地として脚光を浴びている。人口も急速に増え、また、北京などからの直行便も開設されている。鉄路においては、コルラとトルファンを結ぶ南彊鉄道が1984年に開通し、さらにコルラからカシュガルまで工事が、1999年に完成した。トルファン~カシュガル間は1451キロ。
<コルラ故城>(庫爾勒故城)
三つの故城が確認されている。一つは市の南方1.5キロ。「玉子干旧城」と呼ばれる。周囲約1020メートル。ただし城壁はすでに崩壊している。城内に土を盛り上げた台があり、唐代のものと考えられる淡紅色の陶器の破片が散乱していた。
二つめは、町の東北3キロ。「羊達克沁旧城」という。周囲330メートル。青灰色の陶器の破片が多く見られる。
三つめは、「玉子干旧城」の南。名を「狭爾乱旦」という。周囲1080メートル。ここでも、「羊達克沁旧城」と同様、青灰色の陶器の破片が見られた。城壁は崩落している。
<鉄門関>(てつもんかん)
コルラの市街の北8キロ。孔雀河の上流の峡谷の出口を利用した砦。トルファンからタリム盆地へ、あるいは、タリム盆地からトルファンへ入る要衝であり、守りが堅固であることから「鉄門関」と名付けられた。
始まりは四世紀後半の前涼の時代。
岑参は唐の詩人。西域に従軍生活を送り多くの辺塞の詩を残したが、その岑参が言う。「橋は千仞の危うきにまたがり、路は両崖のせまきにわだかまる」と。
↑ ページのトップへ
《クチャ》(庫車)
 紀元前からのオアシス都市。漢の時代には「亀茲(キジ)国」と呼ばれた。自らも金属を産し、また、天山南路最大のオアシスとしての中継交易で栄えた。
紀元前からのオアシス都市。漢の時代には「亀茲(キジ)国」と呼ばれた。自らも金属を産し、また、天山南路最大のオアシスとしての中継交易で栄えた。
後に匈奴の支配下に入り、後漢の時代には班超に降り西域都護府が置かれた。「亀茲国」の滅亡は七世紀。唐に滅ぼされる。
九世紀半ばには、北方の草原から移住してきたウイグル人が国を建て、亀茲ウイグルを名乗った。
クチャで有名なのは音楽と仏教遺跡。音楽は、「亀茲楽」と呼ばれる。中国の隋・唐時代、西域の音楽がもてはやされたが、その中心が亀茲楽であった。琵琶、ハープ、ひちりき、横笛、簫など多彩が楽器を用いてエキゾチックな音楽を演奏した。
 また、仏教遺跡に関しては、キジル、クムトラ、スバシなどの大規模の仏教遺跡を多く抱える。鳩摩羅什(350~409)は中国仏教史上、最も大きな影響を残した高僧の一人であるが、鳩摩羅什はこの地に亀茲王の妹を母として生まれた(父はインド人)。仏典の漢訳にも力を注ぎ、「般若経」「 法華経」「維摩経」などの大乗経典35部294巻におよぶ翻訳を完成させたという。
また、仏教遺跡に関しては、キジル、クムトラ、スバシなどの大規模の仏教遺跡を多く抱える。鳩摩羅什(350~409)は中国仏教史上、最も大きな影響を残した高僧の一人であるが、鳩摩羅什はこの地に亀茲王の妹を母として生まれた(父はインド人)。仏典の漢訳にも力を注ぎ、「般若経」「 法華経」「維摩経」などの大乗経典35部294巻におよぶ翻訳を完成させたという。
地名がクチャとなったのは、18世紀半ば、清朝のジュンガル部への遠征・平定の後のことである。
<亀茲故城>(きじこじょう)
 市の中心から西へ一キロほど。土で築いた城壁の跡がある。周囲は七キロ。漢の時代の亀茲国のもので、後に唐が西域都護府を置いた場所でもあると考えられている。
市の中心から西へ一キロほど。土で築いた城壁の跡がある。周囲は七キロ。漢の時代の亀茲国のもので、後に唐が西域都護府を置いた場所でもあると考えられている。
正式な調査が1957年に、中国を代表する考古学者である黄文ヒツにより行われている。出土文物としては、陶片、銅製品、玉製品、亀茲小銅銭など。
<モラナエシディン・マザー>
市の中心から西へ700メートルほどにある墓。マザーは墓。モナラは「聖人の後裔」の意。エシディンが名前。エシディンは、クチャにイスラム教の布教に初めてきた伝道師と言われる。十四世紀の半ばのことである。祖先はプラハの出身という。
エシディンはクチャとその周辺で伝道をし、この地に没した。
墓は、大門、礼拝堂、墓門、墓室などからなり、いずれも緑色の琉璃磚で装飾が施された典型的なイスラム建築になっている。現在の姿になったのは、十九世紀後半である。
<クチャ大寺>
 クチャの中心から西へ4キロ。クチャ河をこえて行く。
クチャの中心から西へ4キロ。クチャ河をこえて行く。
三千人を収容できる礼拝堂を持つこの地域最大のイスラム寺院。十六世紀の創設と伝える。
宣礼塔楼、大殿、無名墓、学経房、宗教法廷などの建築からなる。特に宗教法廷が残されているのは珍しい。
<クチャ博物館>
クチャ大寺の西北600メートル。「出土文物館」「織物館」「亀茲壁画館」「古銭幣館」からなる。スバシ故城で発掘された女性の骸骨、亀茲の銅銭、クムトラ千仏洞の壁画の模写などが展示されている。特に、クムトラ千仏洞の壁画の模写は非常に精密であり、また、見学には新彊ウイグル自治区文化部に申請をして許可を得なければならないこともあり、模写とはいえ、じっくり見る価値がある。
<スバシ故城>
 クチャの市街から東へ23キロ。チョルタク山の南麓にある。広漠とした沙漠にクチャ河が流れ、その流れに分けられるかのように、東西ふたつの寺が向かい合って建てられていた。
クチャの市街から東へ23キロ。チョルタク山の南麓にある。広漠とした沙漠にクチャ河が流れ、その流れに分けられるかのように、東西ふたつの寺が向かい合って建てられていた。
玄奘三蔵が『大唐西域記』に記したチョグリ大寺だと考えられている。もしそうだとすれば、唐代には亀茲国最大の寺院であったところになる。
周りの壁はすでに倒壊してないが、三つの塔、楼、僧坊、仏洞などの遺構が残り、当時の壮大な規模を彷彿とさせる。
東区は、東西146メートル、南北535メートル。仏堂、北塔、僧坊などがある。西区は、東西170メートル、南北685メートル。南塔、仏堂、仏洞などがあり、仏洞の内部には人物壁画と亀茲文字による題記が記されている。また、このほか、漢~唐代の貨幣や泥塑仏像、木簡や紙片が出土している。
現在見学が出来るのは、西区だけである。
<キジル千仏洞>(キジルせんぶつどう)
 クチャの西75キロ、ムザルト河の北岸に穿たれた石窟寺院。236の石窟が確認されている。クチャ地区で最も大規模な石窟群である。開削の年代は三世紀から宋の時代。
クチャの西75キロ、ムザルト河の北岸に穿たれた石窟寺院。236の石窟が確認されている。クチャ地区で最も大規模な石窟群である。開削の年代は三世紀から宋の時代。
窟中の塑像はほとんど破壊されたか持ち去られてしまっている。また、壁画が残っている窟は74。
壁画の主なテーマは、因縁物語、仏教説話、本生説話などの仏教故事。そのほか、当時の生活や風習を題材にしたものの少なくない。第38窟の伎楽図には、琵琶をひいたり横笛を吹く姿が描かれている。
別名「青い石窟」とよばれることもあるが、それは、壁画の多くに青色が使われていて、それがひときわ鮮やかな印象を見る者に与えることによる。
この青色の顔料は、ラピスラズリである。ラピスラズリ。日本では瑠璃と呼ばれる。古代エジプトでもメソポタミアでも珍重された稀少な石である。これをふんだんに使った壁画がキジル千仏洞の一つの特徴であるのだが、このラピスラズリはクチャ付近では産しない。これを産するのは世界で一か所、アフガニスタンである。クチャから隔たること3000キロ。この一事をもってしても、クチャの繁栄、東西交易の盛んさ、そして千仏洞に注ぎ込まれた当時のクチャの人々の情熱の大きさが知れよう。
岩山の麓には近年鳩摩羅什の像が建てられている。キジル千仏洞と鳩摩羅什との間には直接的な関係はないが、鳩摩羅什がクチャの出身であること、そして彼が活躍をした時期と、千仏洞が盛んに開削された時期が重なることの縁による。
<クムトラ千仏洞>(クムトラせんぶつどう)
クチャの西南30キロ。ムザルト川の渓谷の東の断崖に掘られた石窟群。蜂の巣のように窟が穿たれているが、その数、112。南北に分かれ、南に32窟、北に80窟。三世紀から十一世紀にかけての開鑿、最も多いのはウイグル高昌国(531~640年)の時である。
窟内はすべて破壊されているが、保存の良い状態の壁画が三十余残されている。
<クズルガハ千仏洞>(クズルガハせんぶつどう)
クチャの西10キロ。5~6世紀に開鑿され、キジル千仏洞よりはややおそい。現在残されているのは46窟。仏陀の本生説話と因縁説話、捨身飼虎図などの他、飛天や武官を描いたものなどがある。
<クズルガハ烽火台>(クズルガハほうかだい)
 クチャの西10キロ。漢の時代の烽火台。漢は班超を使わし西域諸国を平定するが、その時、クチャには西域都護府が置かれる。匈奴との戦い、諸オアシス都市との抗争の最前線での情報伝達のために多くの烽火台が築かれたが、そのなかでも最も古い部類にはいると考えられれている。
クチャの西10キロ。漢の時代の烽火台。漢は班超を使わし西域諸国を平定するが、その時、クチャには西域都護府が置かれる。匈奴との戦い、諸オアシス都市との抗争の最前線での情報伝達のために多くの烽火台が築かれたが、そのなかでも最も古い部類にはいると考えられれている。
高さ16メートル。上が展望のための台になっており、それを囲んでいた木の柵を今でも確認できる。
↑ ページのトップへ
《カシユガル》(喀什)
 タクラマカン砂漠の西端。パミール高原の北麓。新彊ウイグル自治区の西南部に位置する。タリム盆地の北縁に沿って続く天山南路の西端でもあり、タリム盆地の南縁の西域南路の西端でもある。
タクラマカン砂漠の西端。パミール高原の北麓。新彊ウイグル自治区の西南部に位置する。タリム盆地の北縁に沿って続く天山南路の西端でもあり、タリム盆地の南縁の西域南路の西端でもある。
両道はここで合流し、パミールを越えてインドへ、あるいは、西北に路をとりタシケント・サマルカンドへと続いていった。
カシュガルとは、古代イラン語やペルシャ語で「玉の市場」を意味すると言う。玉とは、勿論、コンロン山脈で産するホータンの玉をいう。あるいは、ウイグル語で「色とりどりの煉瓦で出来た家」の意とも言う。
中国の歴史に登場するのは前漢の時代。疏勒と呼ばれ、西域三十六国のひとつであった。その後、匈奴の支配下に入るが、後漢の時代、一時的にではあるが班超の活躍により西域都護府が置かれる。
九世紀以降にはモンゴル地域より大量のウイグル人が押し寄せてくることになるが、その後のカシュガルの姿を決定的にしたのは、十世紀にカシュガルを拠点にしたカラ=ハーン朝の成立である。ひとつはトルコ化(ウイグル化)でありひとつはイスラム化である。それをカシュガルにもたらしたのがこの王朝であった。
カシュガルと呼ばれるようになったのもこの頃からであると言われる。
 その後、チャガタイ=ハーンの統治以降は、カシュガル=ハーン、
オイラートのジュンガル王国の支配を受け、清朝が支配を確立するのは十八世紀、乾隆皇帝のジュンガル派兵による。清軍のカシュガル占領は1759年である。
その後、チャガタイ=ハーンの統治以降は、カシュガル=ハーン、
オイラートのジュンガル王国の支配を受け、清朝が支配を確立するのは十八世紀、乾隆皇帝のジュンガル派兵による。清軍のカシュガル占領は1759年である。
十九世紀後半から二十世紀にかけては、またその重要な地理的な位置ゆえに、ロシア、イギリスの勢力争いの激突の場となる。両国がカシュガルに領事館を置き熾烈な情報戦が展開された。
現在のカシュガルは、人口22万、ウイグル族がその74%を占める。ウイグル族の他、ウズベク、キルギス、タタール、オロスなど多くの少数民族が暮らしている。
<エイティガール清真寺>(エイティガールせいしんじ)
 市の中心にある中央広場の西北の門にある。新彊ウイグル自治区最大のイスラム寺院。「エイティガール」とはアラピア語とベルシア語の合成語で、「祝祭日に礼拝をする場所」という意味。創設はイスラム暦846年(1426年)と伝える。その後、たびたびの拡張があり、現在の姿になったのは十八世紀。
市の中心にある中央広場の西北の門にある。新彊ウイグル自治区最大のイスラム寺院。「エイティガール」とはアラピア語とベルシア語の合成語で、「祝祭日に礼拝をする場所」という意味。創設はイスラム暦846年(1426年)と伝える。その後、たびたびの拡張があり、現在の姿になったのは十八世紀。
南北140メートル、東西120メートル、面積1万6000平方メートル。
正面には門楼が建つ。高さは12メートル。上部にはコーランがアラビア文字で記されている。門楼の左右には高さ18メートルの円筒
形の尖塔が建つ。壁面にはウイグルの紋様がびっしりと彫り込まれている。なかの主な建物は礼拝堂と教経堂。礼拝堂は面積2600平方メートル、4000人の信者が礼拝をすることができる。
寺院が特に賑わうのはイスラム教の祭日であるグルバン節(犠牲祭)とローズ節(断食明けのお祝い)には数万の信者が訪れる。
<香妃墓>(こうひぼ)
 市の東へ5キロ。ホージャー一族の墓。創建は1670年。アパク・ホージャーが父親ユースフ・ホージャーのために造ったのが始まり。
市の東へ5キロ。ホージャー一族の墓。創建は1670年。アパク・ホージャーが父親ユースフ・ホージャーのために造ったのが始まり。
「ホージャー」とはイスラム教の聖者の称号である。彼ら一族はサマルカンドからカシュガルに移り住んだイスラム教の指導者の家系であるという。そのなかで最も力を発揮したのがアパク・ホージャーで、カシュガルにおいて強力な宗教的政治的権威を獲得した。それ故、彼が父のそばに葬られた後は、「アパク・ホージャーの墓」と言われてきた。
その一族の墓地の中に「香妃の棺」が置かれ、現在は「香妃墓」と呼ばれるようになった。香妃に関する言い伝えはどこまでが真実でどこまでが伝説なのかは不明であるが、現地に伝わる言い伝えとしては次の通り。
カシュガル生まれのウイグル族の名家の娘が清の乾隆帝に嫁いだ。身体からかぐわしい香りを漂わせていたことから「香妃」と呼ばれた。不幸にも病死をしてしまい、遺体は、124人の従者によって担がれ、遠くシルクロードを辿り三年半かかって生まれ故郷のカシュガルまで運ばれここに葬られた、と。
<ユーフス・ハズ・ジャジェブ墓>
カシュガル市の第十二小学の構内にある。ユーフス・ハズ・ジャジェブは十一世紀のウイグル人。カラ=ハーン朝の時代、ベラサグンで生まれ首都、カシュガルで大侍従の地位にあったときにた著した『幸福になるのに必要な知識』という書で知られる。
なぜ、この書が有名かというと、アラビア文字を用いたトルコ語で書かれた世界最初の文学作品、と言われるからである。
なぜ、「アラビア文字を用いたトルコ語」、が問題になるかというと、トルコ人・ウイグル人のイスラム化というテーマに貴重な資料を提供するからである。
九世紀に遊牧トルコ族であるウイグルが甘粛の北のモンゴル草原から大挙してタリム盆地さらには中央アジアのオアシス地帯へ、移住し、定住化する。これは、遊牧史上の一つの謎であるのだが、いずれにしてもこれにより、この地域のトルコ化がおこる。ウイグル人が最初に出会った宗教はマニ教であり仏教であったが、同じ時期、アラビア半島で興ったイスラム教の波が東へ押し寄せてくる。そこで、トルコ人・ウイグル人はイスラム化し、中央アジア、タリム盆地がイスラム化する。そういう大きな歴史のダイナミズムのなかで、「アラビア文字を用いたトルコ語の文学作品」が脚光を浴びることになるのである。
<マフムード・アル・カシュガリー墓>
カシュガルの西南45キロ。マフムード・アル・カシュガリーは、十一世紀のカラ=ハーン朝の貴族。カシュガル出身のトルコ人である。アラビア語で書かれた『トルコ語辞典』で知られる。
これが書かれたのはマフムード・アル・カシュガリーがバクダットに滞在中であるが、彼は、東は東ローマ帝国から西はタリム盆地のオアシス地帯まで、トルコ人の住むところはおよそ遍歴し尽くし、トルコ語の諸方言を採集した。その採取した単語をアラビア語で説明をしたのが『トルコ語辞典』である。
3巻8編からなり、7500語を収録する。
この辞書は次の二点を証明するものだと言われている。
ひとつは、中央アジアのトルコ化。もうひとつは、イスラム世界のなかでトルコ語が、アラブ語やペルシャ語とならんで主要な言語としての地位を持ち始めていた、ということ。
<ハンノイ故城>
カシュガル市から東北へ28キロ。東西10キロ、南北6キロの広大な規模の遺跡である。唐代の疏勒の都城と考えられている。城壁、堡塁、房舎、農地、用水路などの遺構が残されている。
出土された古銭には、唐代、宋代の中国銭のほかアラピア語を鋳ってある四角い穴のあいたアラビア銭もある。
十世紀以降カシュガルにはカラ=カーン朝の都が置かれ、タリム盆地のトルコ化、イスラム化の基地となるが、そのカラ=ハーン朝の初期の都城としても使われていたものと思われる。
<モール仏塔>
カシュガル市から東北へ30キロ。唐代から十世紀頃にかけて造られたと思われる仏塔がある。中国最西端の仏教遺跡とされる。
<カラクリ湖>
カシュガル市から南へ196キロ。中国とパキスタンを結ぶのが中パ公路。その途中にあるのがカラクリ湖である。標高は3600メートル。ムスターグ・アタ(7546メートル)とコングール(7719メートル)に挟まれた高原にある。
ムスターグ・アタは分水嶺になっていて、これより南の川はヤルカンド方面に、北の川はカラクリ川となりカシュガルへ流れる。
紺碧の湖面に、真っ白いコングールが影を映す。
辺りで放牧生活をするのはキルギス族。
高度が高いこと、夏でも気温が低いことに気をつける必要がある。
<バザール>
 西域のバザールの賑わいには独特の味わいがある。紫髯緑眼の人びとが香辛料を売り、ハミ瓜を売り、ナイフを売り、帽子を売り、絨毯を売り、楽器を売る。紫髯緑眼の人びとがそれを買う。
西域のバザールの賑わいには独特の味わいがある。紫髯緑眼の人びとが香辛料を売り、ハミ瓜を売り、ナイフを売り、帽子を売り、絨毯を売り、楽器を売る。紫髯緑眼の人びとがそれを買う。
ただ眺めているだけでもあきることはない。
特にバザールが賑わうのは日曜日。
↑ ページのトップへ
《タシュクルガン》
パミール高原にある。中パ公路のクンジュラブ峠の手前。クンジュラブ峠を越えるとパキスタン。
玄奘三蔵を始め、多くの求法の中国僧がこの路を天竺へむかった。
現在は、イラン系のタジク族が多く住む。
<石頭城>(せきとうじょう)
唐の時代の城壁の跡。周囲は1300メートル。城壁、城門、寺院、住居の遺跡が残る。炭素一四による測定では七世紀半ばから八世紀半ばのものであることを示しており、唐の時代の喝盤陀国の都城跡、同時に同じく唐代の葱嶺守捉城跡であろうと推測されている。
↑ ページのトップへ
《ヤルカンド》(莎車)
漢の時代、莎車と呼ばれたオアシス都市があった。『漢書』に言う。「玉門・陽関より西域に出ずるに両道あり。ゼンゼン(楼蘭)より南山の北にそい、河にしたがい、西行して莎車に至を南道となる。南道は西にから葱嶺をこえれば、則ち大月・安息にいず」。その莎車である。
中国からインドへ向かうにはどうしても通らなければならない町、それがヤルカンドであった。十三世紀、マルコ・ポーロはヤルカンドを西から東へ抜けて行く。「ヤルカンは延長五日行程の国で、その住民の大部分はイスラーム教徒だが、中に些少のネストール派キリスト教徒を交えている」。
↑ ページのトップへ
《ホータン》(和田)
漢の時代の于テン。西域南道の古くからの大オアシスである。玉の産地として有名。崑崙山脈より二条の河が流れてくる。市の西側にカラ=カシュ川、東側にユルン=カシュ川(黒玉川、白玉川と言われる)。ともにタクラマカン砂漠に流れ込むが、これら二つの川の河床から玉がとれる。
玉に対して中国人は古来特殊な神秘性を感じてきた。天と地が創り出す最も高貴なもの。高貴、完璧、節操、不朽の象徴、というように。「君子は玉において徳を比ぶ」などという。
河北省保定で武帝の庶兄、中山王劉勝夫妻の墓が発見された。二人は、金糸で綴られた2500枚の玉の札で作った葬衣に包まれて埋葬されていた。金縷玉衣あるいは金糸玉衣という。肉体の不滅という願いを玉に託している。そればかりではない。口に玉を含ませる。含蝉という。手に豚をかたどった小さな玉を握らせる。玉豚という。
その玉は、ホータンにしか産しなかった。
玉は硬度や比重の違いから硬玉と軟玉の区別がある。硬玉は中国でも産出された。翡翠などが硬玉になる。しかしながら、中国人が尊んだ軟玉は、ホータンでのみ採れたのである。従って、上に述べた中山王劉勝夫妻が纏っていた玉衣の玉も、ホータンから渡ったものであったに違いないのである。
ホータンの玉が大量に中国に入ってくるのは、漢の武帝の西域平定後である。ホータン国は進んで土地の産物を朝貢するようになったという。ただし、中国産の硬玉と違って 皇帝の独占物そして、厳重に監視された。漢の西の果ての関所を玉門関という。玉の密輸を厳しく取り締まることも役割のひとつであった。
ホータンには、法顕や玄奘が訪れている。大乗仏教が盛んで大きな寺、多くの僧がいると記されている。マルコポーロは、「住民はすべてイスラム教である」と記している。
仏教王国として栄えたホータン国は十一世紀、カラ=ハーン朝に滅ぼされ一挙にイスラム化に向かう。また、カラ=ハーン朝の将軍ユースフ・カドゥル・ハーンは国都ホータンを破壊し尽くし、11キロ離れたところに新都を建設した。それが現在のホータンである。
<ホータン文物管理所>
ホータン地区で発掘された文物が保管・展示されている。発掘された遺跡の数は120箇所というが、玉器、楽器、絨毯、古幣からカロシュティー文字の書かれた木簡、ミイラに至るまで実に多種多様な資料が集められている。
カロシュティー文字とは何かというと、二十世紀初めスタインによってホータンの東北にあるニヤ遺跡、楼蘭などで大量の文書が発見された。木簡、皮、紙、絹などにカロシュティー文字で書かれていたためカロシュティー文書と言われる。王の命令、契約書、個人の書簡などを含むが、三世紀から四世紀の楼蘭やホータンの様子を知る上で貴重な資料となっている。カロシュティー文字は、紀元前三世紀ごろから西北インド、クシャン朝の領土内で使われていたものであり、文書を文字のみならず言語から見ても、サンスクリットの方言のひとつであるブラクリットで書かれている。このことから、三世紀に楼蘭を支配していた民族は、クシャン朝の遺民ではないかとの推測がなされている。
<ヨートカン遺跡>
ホータン市の西方10キロ。文物を含む土層は厚さ3-6メートルのの洪積層に覆われている。ヘディン、スタイン、大谷探検隊など多くの調査が行われた。
スタインのように、ここを漢代のウテン国の国都と考えるものもいるが、まだ、定説になるまでには至っていない。
<マリクワト故城>
ホータン市の南25キロ。ユルン=カシュ川(白玉川)の西岸にある。南北1.5キロ、東西800メートル。かなり大きな遺跡である。高大な土堆と建造物の礎石が残る。陶製の甕から漢の五銖銅銭が大量に発見されたほか唐代までの貨幣が出土している。漢代から唐代まで続いた故城であると考えられる。
また、房舎の遺構より、螺髪のある泥塑仏像の頭部が出土されており、『法顕伝』の「瞿摩帝大寺」、さらには、玄奘の『大唐西域記』の「大伽藍」ではないかと考える学者もいる。
<白玉川>(はくぎょくがわ)
崑崙山脈から流れ出た水は、ホータンの西側をカラ=カシュ川(黒玉川)として、東側をユルン=カシュ川(白玉川)として流れ、ホータンを潤していた。両河は沙漠の中で合流し、ホータン川としてタクラマカン砂漠を縦断して天山南路のアクス附近でタリム川に注ぎ込む。
また、両河はそれぞれ色の違う玉を、雪解け水とともに崑崙山脈から運びだす川でもあった。今は、カラ=カシュのほうは水が流れておらず、ユルン=カシュでのみ玉の採集が行われている。
↑ ページのトップへ
《ニヤ》(民豊)
ホータンの東300キロ。沙漠の中の小さな町。人口三万。漢の時代、西域三十六国の精絶国があった遺跡が北の砂漠に残る。
<ニヤ遺跡>(ニヤいせき)
現在のニヤ県の北部、ニヤ河の下流域にあった遺跡。ニヤ県からは砂漠のなか、120キロの行程になる。
最初に発見をしたのはイギリスのスタイン。1901年のこと。漢代の精絶国の遺跡とされる。
遺跡は南北25キロ、東西7キロの広がりを持ち、仏塔、住居、役所と見られる建物、水路、畦などの跡が残る。
建物の土台には麦わらと牛糞を混ぜ合わせた土が使われ、壁にはタマリスクを編んでその上から泥を塗って造られている。建物の中には炉や、竈も残り、火が当たる部分の土の色が赤く変色した様子も残っている。
多数のカロシュティー文書も出土され、後漢の時代にはゼンゼン国(楼蘭)に属していたこと、三世紀には理由は分からぬがこの都市が放棄されたこと、インド・ガンダーラ地方のタキシラからの移住民がいたことなどが知れる。
──ニヤ東漢墓(ニヤとうかんぼ)
ニヤ遺跡の中の墓地。東漢は後漢のこと。夫婦合葬墓で、木棺のなかから男女一対二体のミイラが発見された。墓主は漢族ではないが、身につけた錦袍には「万世如意」「延年益寿大宜子孫」などの漢字が織り込まれている。
↑ ページのトップへ
《チェルチェン》(且末)
タリム盆地の東南の縁にある。チェルチェン川流域のオアシス都市。前漢の時代には西域三十六国に含まれる且末国と小宛国があった。その頃の住民はイラン系であった。
紀元二世紀の後半から三世紀にはゼンゼン(楼蘭)の支配下に入る。その頃のゼンゼン(楼蘭)は、西北インドから移住してきたクシャン人が支配をしていた。
マルコポーロは『東方見聞録』のなかで、チェルチェンについて、敵が来たら住民は妻子と家畜をつれて砂漠のなかに逃げ込み、彼らだけが知っている水の在処でしばらく暮らす。「彼らの残した足跡は風があとかたもなく砂で被い去って、人一人・家畜一匹すら通ったとは見えなくなるから」(平凡社版・愛宕松男訳)と書いている。
↑ ページのトップへ
《チャリクリク》(若羌)
タリム盆地の東の端の小オアシス。チェルチェンの東240キロである。西域南路と青海省を結ぶオアシスである。古くは楼蘭国に支配されていた。
<ミーラン遺跡>(ミーランいせき)
チャルクリクの東75キロ。1907年、イギリスの探検家スタインによって発見された。何よりも世界を驚かせたのは、仏教寺院跡から発見された壁画に描かれた有翼天使像。中国では非常に珍しいもので、他の地域ではいまだに出土されていない。ミーラン特有の造形である。スタインは、そのほとんどを持ち出した。その後、日本の大谷探検隊の橘瑞超も持ち出しており、現在、東京国立博物館に保管されている。
これらは、ゼンゼン王国(楼蘭)全盛期(3世紀~4世紀)にミーランがその版図にある時代のものだと考えられている。
遺跡は東西に7キロ、南北に5キロの範囲で広がっているが、大きくふたつの部分に分けて考察すべきだとスタインは言っている。ひとつは寺院の址。ひとつは城郭の址。経営された時代が違う、と。
上に述べたのは寺院の址に関してである。城郭の址は、それから500年ぐらい経ってからのこと、八世紀から九世紀、チベット族の吐蕃王国が新彊に勢力を張っていた唐代後期の遺跡と推定される。周囲308メートル、チベットの木簡が出土されており、こちらは、であると思われる。
↑ ページのトップへ
《楼蘭》(ろうらん)
「往古、西域に楼蘭と呼ぶ小さい国があった」。井上靖の『楼蘭』の書き出しである。
楼蘭が中国の史書に初めて登場するのは、『史記』「匈奴伝」。匈奴の王・冒頓単于が漢の皇帝・孝文帝(在位:紀元前180~157年)に宛てた手紙の中で、自らの威を誇るために列挙した彼ら支配する西域の国々の一つとして書かれている。
「天がお立てになった匈奴の大単于は、敬しみて皇帝に挨拶を送る。お変わりないか。(略)天の降したもうた福運によって、軍官卒はすぐれ、戦馬は力強く、月氏を滅亡させ、全員を斬り殺したり降伏させたりした。楼蘭・烏孫・呼ケツおよびその近辺の二十六か国を平定し、すべて匈奴の領土とした」(岩波文庫/小川環樹・今鷹真・福島吉彦訳)、と。
玉門関を西に向かう隊商が最初に出会うのオアシス、ここよりタリム盆地の北縁を天山山脈の南麓に沿って進む天山南路(西域北路)と、タリム盆地の南縁を崑崙山脈の北麓に沿って進む西域南路の二路に分岐する接点に当たる重要さより、常に匈奴と漢の双方からの圧迫に苦しみ続けた。
紀元前七十七年、前漢により名をゼンゼンと改めさせられ、また、三世紀ごろの支配階級はもとの楼蘭人ではなく、西北インドのクシャン朝の遺民に変わっていたと考えられているが、その中でも栄衰を繰り返しながら、最盛期の三世紀初めには東はロプ・ノール西北岸の首都クロライナから西はニヤ遺跡までを版図とする広大な国になっていた。四世紀から五世紀は前涼・前秦・西涼・北涼・北魏などに入貢をするが、445年に北魏により征服される。
ゼンゼンとしてはこれで滅ぶが、オアシスとしてはその後もしばらくは余命を保つが、七世紀以降は、どの史書からも姿を消す。
その楼蘭が再び人びとに姿を現すのは、1900年、ヘディンの発見によってである。
<楼蘭故城遺跡>(ロウランこじょういせき)
ロウラン王国の都であったクロライナの都城跡。1900年にスウェーデンの探検家ヘディンによって発見された。七世紀以降あらゆる歴史から姿を消してから、1300年ぶりに忽然と姿を現した。
城壁、仏塔、住居、水路などの遺構が残る。
城壁はほぼ正方形で一辺は約330メートル。仏塔は城内の東の部分にあり現在の高さで10.4メートル。日乾し煉瓦と木材とタマリスクの枝で築かれている。 住居はすべて崩壊しているが、残る壁のあとから泥をタマリスクの枝で挟うようにして造られていることが知れる。
故城の周囲には仏教寺院や烽火台のあと、さらには古墳群がある。スタインは1914年に多くの墓を発掘し、漢の時代と思われる墓から毛織物や銅鏡、漆器などを出土している。また、ヘディンは1927年の調査で、若い女性のミイラを発掘。井上靖の『楼蘭』は、これに材を得た。
1980年、中国の調査隊は、3800年前と測定された女性のミイラを発掘。
<ロプ=ノール>
チャルクリクの北。タリム河の支流が注ぎ込んでいた塩水湖。『史記』では「塩湖」と呼ばれ、西域への探索から戻った張騫が武帝にこう報告する。ホータンから西では川はすべて西に向かって流れアラル海に注ぎ、ホータンから東では東に向かって流れロプ=ノールに注ぐ、と。『漢書』は「蒲昌海」と呼び、「広さは300里、湖水は澄み、冬夏を通じて水位が安定し、無数の水鳥が湖面に生息する」と言う。
ロプ=ノールが世界の人びとの関心を集めたのは、二十世紀初頭、ヘディンが、この湖を「さまよえる湖」と呼んでからである。彼は、こう考えた。タリム河の河道変遷のため湖は南北へ大きく移動する、と。そして、ロプ=ノールの湖畔に栄えた楼蘭の滅亡をその湖の移動と関連づけ、移動の周期を千六百年とした。
現在では支持されることはないが、砂に埋もれた「楼蘭」の発見と「さまよえる湖」説、十九世紀から二十世紀にかけての西域探検の時代を象徴するロマンであった。
いまは完全に枯渇し、干上がった河床をさらすだけである。
<土垠遺跡>(どこんいせき)
楼蘭故城の東北50キロ。1930年代黄文弼によって発見された遺跡。
楼蘭を守るための狼煙台を含む軍事基地。台を土で築き、頂部に烽火用の薪が蓄えられ、将兵の住居も備えられている。漢の時代の木簡が出土している。
孔雀河のロプ=ノールへの流入口にあたり、船着き場もあったものと考えられる。
↑ ページのトップへ
|
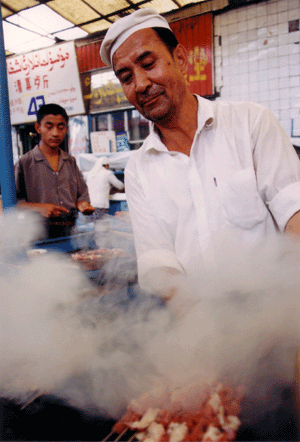 中国31の省・自治区・直轄市のなかで最も面積が広く、全国の六分の一を占め、日本全土の四倍をこえる。
中国31の省・自治区・直轄市のなかで最も面積が広く、全国の六分の一を占め、日本全土の四倍をこえる。 漢王朝以来、東西の交通路が開かれ、人や物の往来のみならず、宗教、文化の通り道となった。そのため多くの史跡を残す。
ウルムチは比較的新しい街で、18世紀の後半、清朝のジュンガル部遠征以降、ここ(当時の地名は迪化)を西域管轄の中心にしてからのことである。上に述べた新彊省の成立はこのことをいい、1884年のことである。
漢王朝以来、東西の交通路が開かれ、人や物の往来のみならず、宗教、文化の通り道となった。そのため多くの史跡を残す。
ウルムチは比較的新しい街で、18世紀の後半、清朝のジュンガル部遠征以降、ここ(当時の地名は迪化)を西域管轄の中心にしてからのことである。上に述べた新彊省の成立はこのことをいい、1884年のことである。 天山山脈の南東麓、トルファン盆地の中央にあるにあるオアシス都市。トルファンはウイグル語で「くぼんだ土地」の意。市の南にあるアイディン湖は、湖面が標高マイナス154メートル、世界で二番目に低い所にある湖である。一番は死海でマイナス399メートル。
天山山脈の南東麓、トルファン盆地の中央にあるにあるオアシス都市。トルファンはウイグル語で「くぼんだ土地」の意。市の南にあるアイディン湖は、湖面が標高マイナス154メートル、世界で二番目に低い所にある湖である。一番は死海でマイナス399メートル。 北へ向かえば天山の北麓に、南に向かえば天山南路。その地理的な位置より、古くからシルクロード上最も重要な拠点のひとつであった。中国の前漢の時代には交河故城を王城として車師前国が栄えていた。玄奘三蔵法師がインドへ向かう途中立ち寄った時に栄えていたのは高昌国。唐は、その高昌国を滅ばしここに安西都護府を置く。その後、チベット、西ウイグル国、モンゴル、東チャガタイ=ハン国、カシュガル=ハン国、ジュンガル部が支配するところとなった。
北へ向かえば天山の北麓に、南に向かえば天山南路。その地理的な位置より、古くからシルクロード上最も重要な拠点のひとつであった。中国の前漢の時代には交河故城を王城として車師前国が栄えていた。玄奘三蔵法師がインドへ向かう途中立ち寄った時に栄えていたのは高昌国。唐は、その高昌国を滅ばしここに安西都護府を置く。その後、チベット、西ウイグル国、モンゴル、東チャガタイ=ハン国、カシュガル=ハン国、ジュンガル部が支配するところとなった。
 紀元前からのオアシス都市。漢の時代には「亀茲(キジ)国」と呼ばれた。自らも金属を産し、また、天山南路最大のオアシスとしての中継交易で栄えた。
紀元前からのオアシス都市。漢の時代には「亀茲(キジ)国」と呼ばれた。自らも金属を産し、また、天山南路最大のオアシスとしての中継交易で栄えた。 また、仏教遺跡に関しては、キジル、クムトラ、スバシなどの大規模の仏教遺跡を多く抱える。鳩摩羅什(350~409)は中国仏教史上、最も大きな影響を残した高僧の一人であるが、鳩摩羅什はこの地に亀茲王の妹を母として生まれた(父はインド人)。仏典の漢訳にも力を注ぎ、「般若経」「 法華経」「維摩経」などの大乗経典35部294巻におよぶ翻訳を完成させたという。
また、仏教遺跡に関しては、キジル、クムトラ、スバシなどの大規模の仏教遺跡を多く抱える。鳩摩羅什(350~409)は中国仏教史上、最も大きな影響を残した高僧の一人であるが、鳩摩羅什はこの地に亀茲王の妹を母として生まれた(父はインド人)。仏典の漢訳にも力を注ぎ、「般若経」「 法華経」「維摩経」などの大乗経典35部294巻におよぶ翻訳を完成させたという。
 タクラマカン砂漠の西端。パミール高原の北麓。新彊ウイグル自治区の西南部に位置する。タリム盆地の北縁に沿って続く天山南路の西端でもあり、タリム盆地の南縁の西域南路の西端でもある。
タクラマカン砂漠の西端。パミール高原の北麓。新彊ウイグル自治区の西南部に位置する。タリム盆地の北縁に沿って続く天山南路の西端でもあり、タリム盆地の南縁の西域南路の西端でもある。 その後、チャガタイ=ハーンの統治以降は、カシュガル=ハーン、
オイラートのジュンガル王国の支配を受け、清朝が支配を確立するのは十八世紀、乾隆皇帝のジュンガル派兵による。清軍のカシュガル占領は1759年である。
その後、チャガタイ=ハーンの統治以降は、カシュガル=ハーン、
オイラートのジュンガル王国の支配を受け、清朝が支配を確立するのは十八世紀、乾隆皇帝のジュンガル派兵による。清軍のカシュガル占領は1759年である。