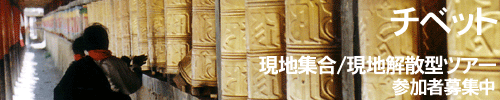<北京・天橋>
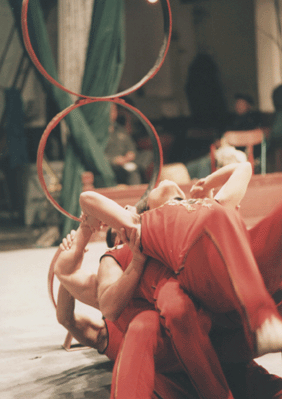 かつて「天橋」というカオスがあった。民衆の享楽のすべてが揃っていた。芝居小屋、露天の市、酒楼、茶屋。芸人がいて、遊女がいて、乞食がいて、遊興の客がいた。
かつて「天橋」というカオスがあった。民衆の享楽のすべてが揃っていた。芝居小屋、露天の市、酒楼、茶屋。芸人がいて、遊女がいて、乞食がいて、遊興の客がいた。
「天橋の芸人雲霞の如し」。
一尺の剣を呑む者。石を頭で割る者。白砂を手でまいて地面に達筆の字を書く者。蛙や蟻を使った芸もあった。懐から瓶を取り出し、「体操」と叫ぶと、黒と褐色の二色の蟻が何百匹も出てくる。混ざり合って動いているが、「整列」と叫びながら米粒をまくと、黒と褐色の二列に分かれ整列をする。さらに、「終わり」と声を掛けると、瓶に戻る。不思議な芸だ。その後、後を継ぐ芸人も蟻もいない。
 芸人たちは己の一芸にすがり口に糊した。人々はその芸に一日の憂さを晴らした。
芸人たちは己の一芸にすがり口に糊した。人々はその芸に一日の憂さを晴らした。
酒旗戯鼓天橋市
多少游人不憶家
清末の詩人、易順鼎の《天橋曲》の一節である。酒屋の旗、芝居の太鼓。ここに遊ぶは家を憶わず。天橋を歌って巧みだ。切ないほどだ。家を本当に忘れている者は、「家を憶わず」とは言わない。生の切なさを埋めることのできる享楽などありはしない。だからこそ、享楽に浸りたい。そういう切なさなのだ。
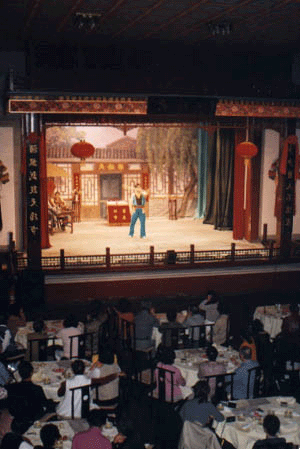 前門から南へ一キロ。天橋の名は残るが、かつての賑わいもさんざめきも今はない。そのなかで、昔の天橋を唯一偲ばせるよすがは、「天橋楽」である。一階には舞台と客席、二階には桟敷席を回廊状に巡らす構造は、往事の劇場そのままである。演しものは大分変わった。剣を呑むやら石を割るやらは流行らない。輪くぐりや鳥の鳴き真似などの品の良いものが主流だ。それも時代の流れというものだろう。それでも、舞台の両脇には《天橋曲》のあの詩句が掲げられ、天橋のかつての輝きの残光を放ちながら、享楽への憧れと切なさを今に語り継いでいる。
前門から南へ一キロ。天橋の名は残るが、かつての賑わいもさんざめきも今はない。そのなかで、昔の天橋を唯一偲ばせるよすがは、「天橋楽」である。一階には舞台と客席、二階には桟敷席を回廊状に巡らす構造は、往事の劇場そのままである。演しものは大分変わった。剣を呑むやら石を割るやらは流行らない。輪くぐりや鳥の鳴き真似などの品の良いものが主流だ。それも時代の流れというものだろう。それでも、舞台の両脇には《天橋曲》のあの詩句が掲げられ、天橋のかつての輝きの残光を放ちながら、享楽への憧れと切なさを今に語り継いでいる。
(中日新聞・東京新聞の2001年11月04日日曜版に掲載)